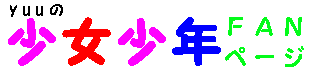十河太一編~0と1の間~後編
ラジオ局に届いた達筆な文字のハガキ。それが零那と繋がる第一歩となる一通だった。 小中学生がメインターゲットのラジオ『千明の不可思議アイランド』に届くハガキは、字が上手いと思う子は少なく、特に女の子からのハガキは丸文字のかわいらしい文字で書かれていることが多かった。 そんな中、達筆で書かれたそのハガキは目立っていた。内容はいたって普通の感想メッセージ。ただ、そんな感想が直接届くことも少ないのでそのハガキはうれしかった。 普段は文面だけ見て採用するハガキを決めるものの、なんとなく名前が気になってハガキをめくり、宛名面を見た。心臓がドキッと跳ね上がったようだった。 『毛利零那』 差出人として確かにそう書かれてあった。つい最近知った、小さい時に見て憧れていた女の子の名前だ。 嬉しくて思わず村崎さんに報告する。うまいこと仕事の話に切り替えられたけど、仕方がない。零那に近づくために素直にしたがうことにした。 さて、問題はこのハガキだ。普通、ハガキにはペンネームが書いてあるものだけど、このハガキにはどこにも書かれていなかった。 ラジオの感想が書いてあるだけなので、採用してもらおうと思ったわけではないのかもしれない。実際、質問でも相談でもリクエストでもないハガキを読み上げたことは無い。 でも、この一歩を逃すわけにはいかない。そう思って、放送作家のBAKUさんにも許可をもらい、そのハガキを放送開始してすぐに読み上げた。 「今日は最初にスタジオに届いたハガキを紹介します。神奈川県の零那ちゃん!」 フルネームは避けておいた。ミュージカルにでてるぐらいだから、その業界では名を知っている人もいるかと思ったからだ。 「…等身大の意見も言ってくれるのもいいし、千明ちゃんはとても親身になって考えてくれるので、いつも楽しみに聴いています…」 ハガキに書いてある内容を読み上げる。こんなふうに思ってくれてるのかと驚いた。 「零那ちゃんありがとう! こうやって思ってもらえるなんてうれしいな。また、おハガキお待ちしています!」 最後にハガキの催促のメッセージも入れておいた。多分、不自然ではないと思う。零那にこの思いが届いてほしいと思った。 その後、思いが届いたのか、最初からそうするつもりだったのか分からないが、零那からハガキがちょくちょく届くようになった。 だが、それからいろいろあって零那の家にいって声がでないことを知り、説教臭いことを言ってしまってからハガキは来なくなった。前回のハガキには『また手紙書きます』とあったので、また送るつもりだったはずだ。 完全に嫌われた。全然、「親身になって考える」ことなんてできなかった。ただ、一方的に自分の意見を言っただけだ。嫌われて当然かもしれない。 ただ、ここでふと疑問に思った。そもそもなぜ、零那はあんな何の変哲もない感想のハガキを送ってきたのか。 ハガキに感想が書いてあるのはよくあることだけど、だいたい質問やリクエストなんかも一緒に書いてある。零那が送ってくれたハガキは感想だけだった。 『等身大の意見も言ってくれるのもいいし、千明ちゃんはとても親身になって考えてくれるので、いつも楽しみに聴いています』 もしかしたら、本当は零那も悩みがあるんじゃないか。部屋に閉じこもっている零那が送ってくれたハガキは、多分、零那からのSOSなんじゃないか。 そう考えると、あきらめきれなかった。なぜ零那は声をださなくなったのか。どうやったら声を出そうと思うのか。日夜、そんなことばかり考えていた。 そんな時、阿僧から告白を受けた。正直、うれしくはあったけど、頭の中は零那のことで頭がいっぱいで、誰かと付き合うとかそんなことは考えられなかった。オレは、申し訳ない気持ちでいっぱいになりながらも、付き合えないと謝罪した。 そんな百花から零那について話すと、「声が出たほうがうれしいって思えることがあれば」とアドバイスを受け、その後、ミュージカルのオーディション要項を渡されたオレは、零那と一緒にでようと決意して、再び零那の家へむかった。 零那自身、あんなハガキを出してきたということは、声をだせるようになりたいと心のどこかでは思ってるはずだ。そのきっかけが無かっただけだろう。 後は、オレの思いが届くのを祈るだけだった。また、『帰って』と断られるかもしれない。だけど、これしかチャンスはないと思えた。 結果的に、零那とオーディションを受けることが決まった。あの時、零那が部屋に閉じこもったままだったらもうちょっと時間がかかっていたと思う。 胸に飛び込んできたときに言った「ありがと」という小さなか細いささやきは一生、忘れないと思う。今までよりもさらに、オレにとって愛しい存在だと思わせた。 ただ、これはまだ最初の一歩にすぎない。ここからオーディションを受けて合格しなければならない。正直、現状でほとんど声がだせない零那が受かるかどうかは分からない。可能性としては低いと思う。 今の零那は例えていうなら、羽をケガした小鳥だ。飛びたくても飛べないし、一人では勇気もでない。オレはその小鳥を、飛び立てるようになるまで全力でサポートする。零那のためならなんだってやる。そう決意した。 そう決めてからオレは仕事がない日は毎日のように、学校帰りに零那の家に行くようになった。千明としてオレが零那の家に到着すると、零那はいつも笑顔でかけよってくれた。一生懸命、何かを伝えようとするが、1メートルしか離れていなくてもよく聞こえないほどかすかな声。そのまま悔しい顔をした零那は耳元に近づき、「うれしい」。そうつぶやいた。耳元でささやかれたせいか、すこし耳がくすぐったい。 オレだって、そうだ。零那とこんな近くでいることが何よりうれしかったし、幸せだった。このためにオレは産まれてきたんじゃないかと思うほどだ。零那がラジオを聴いて、ハガキを送ってくれて、本当によかったと思う。 「零那ちゃん…。いや、零那…。多分、オーディションに合格するにはいろんな困難があると思う。辛いこともあると思う。でも、私は零那と一緒にこの舞台に立ちたい。歌って踊るところを見たい。これは、私のワガママかもしれないけど、一緒にがんばってもらえるかな?」 零那は小さくうなずいた。 まずは発声練習だ。最初にオレが零那のお母さんが弾くピアノにあわせて声をだす。続いて零那の番だ。一生懸命に声をだそうとするが、全くでてこない。しまいには、座り込んでしまった。歯を食いしばって泣いているようにも見える。 「大丈夫。その思いはきっと伝わるよ。オーディションには間に合わなくても本番までには声がだせるようになればいいから、今は前向きにいこ!」 その言葉で零那は笑顔になった。この笑顔を大切にしたい。オレはそう思った。 一通り練習をして、そろそろ帰らなければいけない時間になった。 「明日は仕事で来れないかもだけど、また明後日来るからね。零那もがんばって」 それだけ告げて帰ろうとすると、急に零那が顔を近づけてきた。咄嗟のことだったのでビックリして胸が高鳴る。「ありがと」。ただそれを言うためだけに顔を近づけたわけだけど、かすかな声しかでないから仕方ない。ただ、その度に心臓の鼓動が早くなるのが分かった。多分、顔も赤かったと思う。正直、抱きしめたいとすら思った。今のオレは千明、女なのだから、そんなこと思っちゃダメだと思いなおす。 零那の家をでて数メートル歩いたところで、一度振り向いて家の方を見た。ありがとうと言いたいのはこちらのほうだ。零那に会いに行くのは、半分は自分のためだ。零那と何よりも舞台に立ちたいと思っている。そのために女の格好してるといっても過言ではない。 ただ、こんなことはいつまでも続けられないことぐらい分かる。中学になったら声変わりする。早かったら後1年ぐらいで声変わりするかもしれない。最悪、これが最初で最後のチャンスかもしれないとさえ思えた。 そして、オーディションの日がやってきた。零那はというと、隣にいたら自然に会話できるぐらいにはなってきた。ただ、そうはいってもミュージカルにでるにはあまりにも声量が少なすぎた。後は、オーディションの参加者と審査員しだいだ。祈るしかない。 オーディションは二部構成。歌唱審査と演技審査。あらかじめ、歌う曲の楽譜と演じる台本が送られてきており、この1週間はその暗記と練習にどっぷりつかっていた。 オーディション参加者は20人ほどで、広めの会議室のような場所だった。声優オーディションでは一人ひとりスタジオに入って演じていたが、今回のミュージカルのオーディションでは、参加者が全員見ているなかでのオーディションになるという。オレは10番、零那は11番の番号を身につけた。これは、そのまま審査を受ける順番になるという。 まずは歌唱審査が始まった。一人ずつ、ピアノの伴奏にあわせて歌っていく。さすがにオーディションにでるだけあってみんな歌唱力が高い。ただ、それでも審査員の反応はいたって普通のものだった。時折、歌唱が終わった後に質問はするものの、特に感想をいうわけではないし、表情の変化も少ない。 これが普通のレベルなのだと思い知らされた。正直、零那の心配をしているどころではない。オレ自身、オーディションの合格は危ういのではないかと今更ながら気づいた。そう思うと、ちょっとだけお腹が痛くなってきた。昔、瞬とでたオーディションを思い出す。 そして、オレの番になる。審査員の前に立って一度、深呼吸をする。少しはお腹の痛みもとれた。きっと大丈夫。 「万丈千明です。よろしくお願いいたします。」 伴奏のピアノの音が鳴る。目をつぶってお腹から声を出した。歌ってる最中は何も考えてない。ただ、自分なりの歌を歌うだけだった。 歌い終わったオレはゆっくりと目を開けた。正直言って、悪くはないと思う。ただ、審査員にどううつったのか検討がつかなかった。 審査員席の真ん中にいる監督らしき人は少し呆気にとられているような顔だった。そのまま拍手をする。 「いやぁ。よかったよ。可愛らしい歌声の中にどこか中性的な魅力を感じさせる。こんな歌声を聞いたのは初めてだ」 ビックリした。さっきまで誰にも感想をいうことなんてなかったのに、思いがけず褒めてもらえた。 「あ、はい。ありがとうございます!」 やった。心の中でガッツポーズだ。 「監督。今はオーディション中なので、そういう感想は後にしてください」 「あ、ああ。そうだったな。すまない」 監督の横にいる人と監督のやりとりがあった。どうやら、基本的に感想は言わないようにしているらしい。 それだけ、よかったと思ってもらえたということだろう。この声はやっぱり武器になる。 次は零那の番だ。零那が審査員の前に立って、ピアノの伴奏が流れる。零那は伴奏にあわせて歌を…、歌っているのだと思う。自分の位置からだと、かすかに歌っているのだろうなということが分かるが、何を言っているのかは全く分からない。ピアノの音にかき消されている。 ピアノの音が止まって、零那はお辞儀をした。同時にオーディション参加者がざわついた。「えっ? 今の歌ったの?」「全然、聞こえなかったけど…」そんな声が聞こえてくる。先ほど、監督に注意した人も、呆れ顔だ。その顔は、感想を言ってるのと同じなのではないかと思う。 「えっと…、今は病気で声が出づらいけど、リハビリ中ということだね?」 監督が戸惑う様子で応募用紙を見て尋ねると、零那はうなづいた。 歌唱審査が終わった後は、15分の休憩が与えられた。 零那の歌唱が終わってからまたお腹が痛くなったオレは急いで女子トイレにかけこんだ。これは、思った以上にまずい。もちろん、零那がうかるというのは難しいと思っていた。ただ、心のどこかでは大丈夫だと思っていたため、現実を見せつけられると辛いものがあった。次の演技審査だって声量が求めらるだろう。ただ、演技審査の練習の際も、零那は思うように声がだせないでいた。 どうすればいいか。幸い、千明は監督に気に入らってもらえたように思える。いっそのことダブルキャストの相手は零那がいいとお願いするか。いや、ダメだ。千明がオーディションで選ばれたタイミングではもう一人も同時に決まってるはずだ。そんな時にそんなお願いをしたら、呆れられだろうし、千明事体、降ろされかねない そう思っていると、洗面台のほうから女子二人の声が聞こえてきた。話の内容からして今回のオーディションの参加者らしい。 「さっきの万丈千明って子、すごかったね。監督も気に入ってたみたいだし。あの子は確実なのかな」 「千明ちゃんいいよね。私、千明ちゃんのラジオ好きだよ。ちょっと嫌なことがあっても、明日も学校行こうって思える。私も千明ちゃんとダブルキャストになれたらいいな~」 思いがけず、自分の話がでてきて照れる。こんないい子を外してくれと言うなんて到底できない。相手だって必死にここまでがんばってきたのだろうから。 「でも、次の子…。毛利零那だっけ? あの子の出番で笑っちゃった。何あのウィスパーボイス(笑)」 「あれじゃあ、最前列でも何も聞こえないよね。あんな子がミュージカルでてきたら、金返せって思う。何であんなのでオーディションでたんだろ? 記念受験?」 「いや、もしかしたら。口が指向性スピーカーなのかも。審査員には聞こえてた」 「何それウケるー」 前言撤回。相手が誰であろうとちょっとでも可能性があれば零那を推す。たとえ、それでオレが降ろされてもいい。零那と出るために受けたんだ。零那と一緒でなければ意味がない。だいたい、一人だけ受かって続けたところで、同時に他のミュージカルをやれる可能性は低い。それなら、別のミュージカルのオーディションを探してまた一緒に受けるだけだ。 トイレからでたオレは手を洗って鏡を見て気合を入れた後、零那の元へ向かった。零那は椅子に座ってセリフの再チェックをしているようだった。 「零那。ここまで来たら悔いのないようにがんばろう。もう、結果なんて気にしなくていい。私も全力で演じてみせる」 オレはそういうと、零那は顔をあげてオレの顔を見て、そのまま笑顔になった。 演技審査の順番は歌唱審査と逆順だという。つまり、零那の次にオレという順だ。 台本には動物たちと戯れる様子の台詞が並んでいた。台詞と簡単な状況説明はあるものの、どういう表現をすればいいかは書かれてない。なので、歌唱審査と比べると人によって表現は様々だった。身振り手振りを大きくするようにする人もいれば、身振りは小さいが感情をこめてセリフを言う人もいる。中にはミュージカルだからか、歌うようにセリフをいう人もいた。 ただ、一つ言えるのは、全員、よく通る大きい声だった。やっぱり、演技審査でも声の大きさは大事なのだろう。 そして、零那の番になる。ここまできたらただ、祈るしかない。少なくとも、後悔する演技だけはしてほしくないと思った。 零那は一度おじぎをして、演技を開始した。台詞はこちらまで聞こえてこない……。違う。何も言っていない。零那は口パクだった。一瞬ヒヤっとした。まさか、台詞を忘れてしまったのではないかと。 ただ、そう思うと同時に、頭の中で不思議な現象が起きた。零那は確かに何も言っていない。だけど、何を言っている場面なのかはっきりと分かるのだ。声さえ聞こえてくるようにさえ感じる。もちろん、それだけなら台詞を記憶していたということもあると思う。だけど、それだけじゃない。その場には零那しかいないはずなのに、まるで動物たちがそこにいるような幻覚に襲われた。 練習中は声の小ささが気になって、その表現力に気が付かなかった。声をださないことで、体の演技のみに集中でき、表現力のすごさを感じ取れた。零那自身、無理して声をださないことで、演技に集中できるのだろう。自分には思いつかなかった。いや、思いついたからってできることじゃない。これが零那の実力なんだ。オレは思い知らされた。 気づいたら頬に涙が伝っていた。感動の涙が半分。悔し涙が半分だ。オレには到底マネできない表現力だ。同時に、先ほどまで、監督にお願いして零那をいれてもらおうと考えたことを恥じた。こんな表現力ある子を放っておくわけがない。そう思えた。 2週間後、ミュージカルの通知が届いた。千明と零那に決まったということだ。 話によると、千明の採用はほぼ満場一致だったらしい。対して、零那にたいしては最後まで反対意見が多かったという。ただ、表現力の高さと役のイメージから監督が推して零那が選ばれたという。 その監督も、もしこれがシングルキャストでの採用だったら、零那は絶対に選ばなかっただろうとのことだ。ダブルキャストだったら、最悪、千明だけでやっていけると。 実際、通知が来る前に一度、事務所に「もしシングルキャストになっても問題ないか」と連絡があったそうだ。相変わらず、こちらの都合を聞かずに「大丈夫です」と村崎さんは伝えたそうだけど、今回の場合は感謝しかない。もし、それを聞いていたら、零那と一緒じゃないと意味がないと断っていた可能性もある。 それからは稽古と練習の日々が始まった。零那は声のリハビリをしながらの稽古ということになる。一生懸命な零那のがんばりに、オレはできるかぎりの時間をかけて一緒に付き添っていった。 そして、公演初日まで残り2週間となった。 この頃には、零那の声はオーディションの時に声が小さかったのが嘘のように、軽やかに声をだすことができていた。少し遠慮がちな声な気もしなくはないが、じゅうぶん本番で通用する声量だった。 「疲れたー」 練習に疲れたオレは一人、監督にOKをもらって少し離れたところにある椅子に腰かけてで休むことにした。零那はまだ少し、歌の練習をしている。本当によくがんばっていると思う。 「だいぶお疲れのようだな」 後ろから声がして振り返った。そこには瞬がいた。 「瞬じゃん。どうしたんだよ?」 「たまたま近くで仕事だったんだよ。村崎さんとすれ違って、近くで練習してるから会ってきたらって。明日も会うんだから別に会う必要もないんだけど、たまには千明の様子でも見とこうかと思ってさ」 瞬はそういうと、歌の練習をしている零那のほうに目をやった。 「毛利零那もすごいよな。去年まで声がでなかったとは思えないよ」 「そうだよな。リハビリをつづけてここまでこれて…。零那はよくがんばったと思う。あの時、オーディションに誘って本当によかった。」 オーディションに誘った時のことを思い出す。あの時、零那がかけよって声にならないほどの小さい声で「ありがと」と言ってくれたことが蘇った。 「やっぱ、初恋の人だし、一生懸命になったんだろうな」 いきなり瞬がそう言って、思わず噴き出した。 「は、初恋って…えっ? そんなこと言ったっけ?」 「そうじゃないのか? てっきりそういうことかと思ってたんけど……」 「いやまあ、確かにそうなんだけど…」 昔ミュージカルで見た零那を思い出す。軽やかなステップで演じていた零那にオレは恋をしたんだと思う。 一瞬、零那と目が合って軽く手を振った。瞬とも目が合ったようで、二人とも軽くお辞儀をしていた。 「ところで、前から気になってたんだけど……」 瞬はそう言って一拍置き、続けた。 「阿僧には別に似てないよな」 阿僧、つまり同じクラスの阿僧百花のことだ。瞬の言おうとしていることは分かる。昔見たミュージカルの『点と線との阿弥陀くじ』の時の零那は確かに阿僧に似ていた。瞬もその写真をネットでみて、阿僧に似ていると思ったらしい。 「うーん。まあ、声が変わるように顔だって少しずつ変わってくるだろうしね。髪は、ウィッグを付けて演じてたんじゃないかな。たまたま、それで阿僧に似た感じになったのかも。」 「確かに、ミュージカルでウィッグつけるって珍しくないか。よくよく考えたら、お前もそうだし」 「いや、これは一応、地毛ってことになってるから」 瞬の言葉に頭に手を当ててそう言った後、二人して笑った。 「オレも、零那だと知る前は、阿僧じゃないかって思ってた時もあったよ。いつか聞こうと思ってたんだけど、聞かなくてよかったよ。実際、違ったわけだし」 「あぁ。それで、阿僧と話すときそわそわしてた時あったのか。」 どうやら瞬はあの時、オレが阿僧のことを気になってるに感づいていたらしい。オレもあの時、瞬が阿僧のこと好きだろうから正直に伝えた方がいいだろうか迷っていた。もしかしたら、瞬も同じ気持ちだったのかもしれない。ただ、オレの初恋は零那だったわけだ。瞬はそんなこともう気にする必要はない。 「で、瞬はどうなんだよ?」 「何が?」 「阿僧とだよ」 「なっ!! だから、オレは阿僧のことなんて別に……」 瞬は顔を赤く染めて、そう反論した。 「いやいや、その分かりやすい反応やめたほうがいいよ。俳優なんだしさ」 「うるせぇ! そうだよ好きだよ。でもオレは、相手がその気になるまで待つタイプなんだよ」 「何だそれ」 照れながらキレた瞬のその発言に思わず笑ってしまった。 「それじゃあ、オレ帰るから。稽古がんばれよ」 「おうっ! ありがとう! またな」 毎日のように学校では会っているものの、久々に瞬と話したような気がした。そういえば最近は就業時間になるとすぐ帰るようにしてるし、休み時間中は疲れて眠ってることも多い。瞬との会話は零那と話すときとは違う楽しさがあった。 「千明ちゃん!」 いつの間にか零那も練習を終えたらしく、オレの隣に腰かけた。 「今の子って、京極くんだっけ?」 一瞬、瞬との会話を聞かれたかと心配する。だいぶ、男っぽい口調になっていたはずだ。 「そうそう。京極瞬。前に一緒に仕事してから仲良くなったんだ」 別に零那に、瞬はクラスメイトだと伝えても問題ないとは思うのだけど、今は千明として話しているわけだしやめておいた。 「前に、あたしの家に一緒に来てくれたことあったよね?」 零那がそう言って思い出す。そういえば、そんなこともあった。 「そうだね。2回目…じゃない。初めて零那の家に行ったときに付き添いでついてきてもらって……」 「あの時はビックリしたなぁ。急にドア越しに千明ちゃんの声が聞こえてくるから。」 「そうだよね…。ごめん。本当、突然だったと思う。あの頃は、憧れてる女の子からハガキが届いて、ずっと会いたいと思ってて思わず行っちゃって…」 「ううん。私のほうこそ、ごめんね。あの時、せっかく来てくれたのに『帰って。』なんて伝えちゃって。でも、本当はとてもうれしかった」 零那のその言葉に少し照れた。そんなふうに思ってもらえていたなんてちょっとうれしかった。あの時は、むしろ嫌われたかと思っていた。あきらめないで本当によかったと思う。 「そういえば前から聞きたかったんだけど、千明ちゃんと京極くんって付き合ってるの?」 いきなり零那がそう尋ねてきて、思わず噴き出した。先ほども似たようなことがあったような気がする。 「いやいや、瞬は本当、ただの友だち。それに、瞬はクラスに好きな子いるみたいだし」 「そっかー。そうだよね。さっきの会話、最後のほうちょっとだけ聞いてたけど、付き合ってるカップルというより、確かに友だちみたいだなって思った」 案外、あっさりと信じてくれた。最後だけ会話も聞かれてたようだけど、特に何も思っていないようだ。 「でもいいなー。クラスに好きな人がいるって。あたしそういう、同級生を好きになるとかちょっと憧れるんだー。昔はそんなこと思わなかったんだけど、千明ちゃんのラジオを聞いてたら学校生活もいいなーってちょっと思ったの。ほら、あたし、声が出なくなってから学校行かなくなったから。声が戻った今でも気まずくて行けてないんだけどね……」 そういえば、前にオーディション会場のトイレで話していた子も学校に行きたくなるようなラジオと言っていた。オレも零那と一緒の学校だったら付き合うなんてあるのだろうかと夢想する。まあ、ありえないことだけど。 「中学に上がったらさ、心機一転して少し遠い学校にでも通ったらいいんじゃないかな。零那なら友だちも、それこそ…、それこそ恋だってすぐできるんじゃないかな」 「うん。そうだよね。ありがとう」 そういいながらも、そこに自分がいないことを考えると複雑な気分になった。その恋の相手は、自分じゃないのだろうから。 そして、ミュージカルが始まった。 始まった当初こそ空席が目立った公演もあったが、徐々に口コミで話題になってお客さんも増え、同時にリピーターとなる人も増えていった。 そのため、当初は1か月程度だった公演期間も3か月、4か月と伸びていって。千秋楽の日を迎えた。 この頃になるとある決意を固めていた。最近、喉の調子が悪い。声変わりだ。もう、千明として活動はできないのだろうと悟った。幸い、ラジオはミュージカルに集中したいという理由でやめさせてもらったし、他にも仕事がない。村崎さんとも相談して、ミュージカルの公演が終わったら、学業優先という適当な理由付けで辞めることにした。 対して零那は1年前に声が出なかったのが嘘のように軽やかに声をだせるようになった。ミュージカル公演が続くとともにさらに声に磨きがかかった感じだ。1年前に傷ついた小鳥のようだと思ったけど、もう十分傷も癒えて一人でも飛び立てるようになっている。千明は引退してしまうが、零那の声が戻ったことは本当によかったと思う。 ただ、零那には引退することを告げることはできなかった。言えない理由は特にない。勇気がでなかっただけだ。 「これからも、ずっと、ず~っと、いっしょにがんばろーねっ!」 終演後、零那がそう言って駆け寄ってきてくれたが、罪悪感でいっぱいで、「…あ、うん…。」としか言えなかった。 引退すると告げたら理由を聞かれるだろうけど、うまく答えられる自信がない。自分は零那に中学になったら学校に通ったらいいと言っておきながら、学業優先でやめるなんて説得力がない。零那も中学から学校に通うことになるなら、学業優先してやめてもいいんじゃないかと言うようにもとらえかねない。零那にはこの先も、その声と演技力で仕事を続けてほしいと思っていた。 もちろん、だからといって本当の理由なんて言えるわけがない。零那は千明が女だと思って接している。男だってことを告げたら、嫌われる。個人的には別に嫌われてもいいが、千明との思い出は零那にとってもいい思い出になってると思う。その思い出を壊したくはなかった。多分、このまま何も告げずに、フェードアウトしていくのがいい。そう思った。 その日の帰り、駅まで見送ってくれた零那と話をした。零那が自分の声がキライだということ。オレももともと自分の声がキライだったということ。そして、大人になるということは声も変わるということ。 「…オレ、零那の声、好きだよ!」 思わず一人称が「オレ」になってしまったが、最後は本来の自分である太一として伝えたかった。不審に思ったかは分からない。だけど、零那はもう千明に会うことは無い。ちょっとだけオレの気持ちが表にでてしまったけど、「オレ」と言ってしまったからといって、男だったとは気づかないとは思う。 「だから、自信もって、ね!」 そう言って、オレは零那と別れた。千明としての最後の言葉になる。零那には自信をもって仕事をつづけていってほしい。それが、オレの零那への願いだった。 季節は巡って春になり、オレは中学に入学した。 零那はあの後も仕事を続けてるらしい。先日、瞬に頼んで調べてもらったところ、春から声優デビューするなど精力的に活動を続けてるらしかった。ちょっとだけ、千明がいないとまた辞めてしまうのではないかと心配になったけど、杞憂に終わったわけだ。少し寂しくもあるが、今のオレにとっては何よりもうれしいことだ。 登校中、バッタリ瞬と出くわす。 「部活、結局なに入るか決めた?」 いきなり瞬は部活の話をしてくる。先日、零那について調べてっもらった後、瞬はついでに入学する中学校について調べた。部活一覧のページをチェックする。『演劇部』という文字が目に入った。 「あっ、ここ演劇部あるのか。また一緒に演劇やれそうだな」 瞬はそう言って目配せした。 「あ…うん。でもまだ、ちょっと迷ってて…」 「入らないのか? もう仕事やめたんだし、部活ぐらいやってもいいだろ?」 「いやまあ、そうなんだけどさ…。千明としてやりきった感があるから、もう演劇はいいかなって…。」 瞬はしばらくオレの顔をじっと見た後、言葉を続けた。 「…そうか。まぁ、お前が好きなことやればいいよ。」 そうは言ったものの、演劇部に入るかどうかは迷っていた。もう千明の時のような声はでないし、あの時のような演技もできない。零那に会うという目的も達成できた。 でも…、と思う。舞台で演技をしていた楽しさとワクワク感は忘れられない。それは、千明としてミュージカルに出た時だけでなく、小学校の演劇クラブでも同じだ。 やっぱり、中学校でも演劇を続けよう。千明の時のような演技はできないかもしれないけど、演劇部でなら問題ないはずだ。 それにまた、瞬と一緒に演劇をやりたいとも思っていた。 「やっぱオレも演劇部かな~。」 オレは演劇部に入ることを決めた。 そうして瞬と一緒に中学校に向かってる最中、ここにいるはずのない人がいるような気がして思わず振り返った。 「千明…ちゃん!」 そこには零那がいた。しかも、同じ中学の制服を着ている。驚きのあまり呆気にとられて、すぐには声がでなかった。 その後、話をしてみると、どうやら瞬のことを調べていたら、小学校が分かり、その校区に一人暮らしとして引っ越してきたらしい。 中学は遠めのところに行ったらいいと言ったのはオレだ。でも、まさか一緒の学校になるなんて、全く考えていなかった。 「でも、よかった。他の中学校だったらどうしようってさっきまで不安だったの。太一くんと出会えて今はすごくうれしい」 零那が『太一』と呼んでくれる。まさか、そんな日がくるとは夢にも思っていなかった。 零那とは残念ながらクラスは離れてしまった。さすがにそうなんでも都合よくいくもんでもない。仕事が忙しいということで、演劇部にも入れないという。残念だけど、仕方がない。だいたい、零那が入ったところで一人浮いてしまうだけだ。零那の実力は、そこらの演劇部にいるようなレベルではない。零那にはもったいないし、だからといってわざとちょっと下手に演じてもらうなんて零那にとっても嫌だろうし、オレとしても嫌だった。 たいして瞬はある程度、仕事をキープしてるそうだから演劇部にも入るようだ。たまに、仕事で来られないこともあるかもしれないというのは、顧問の先生や部長にも了承ずみだという。むしろ、そういう子は大歓迎で、話も聞かせてほしいとのことだった。ちなみに、瞬とも別のクラスになってしまったが、阿僧とは引き続き同じクラスになった。瞬も、阿僧とクラスが別になって残念がっている事だろう。 ただ、クラスが違うことなんてそれは些細な違いでしかない。休み時間になれば会いに行けるし一緒にお昼ご飯を食べることもある。時には、休日に予定をたててでかけることもあった。 零那自身、クラスに溶け込めているようで、友だちもできたようだ。零那にとっても、憧れていた学校生活だと思う。 自分がその中にいるなんて不思議だ。今でも太一として零那と接することができるというのは、夢なんじゃないかと思うことがある。実際、零那と話していると思わず一人称が「私」になって、恥ずかしくなったこともある。なんとなく、千明の頃に戻った気がする。もちろん、あの時とは声が違うし戻れることは無い。 正直、こんな幸せなことってあるんだなと感じる。初恋の人がそばにいて、楽しく学校生活を送ることができている。いつまでもこういうふうにいられたらいいなと思った。 ただ、お互いに好きだと言ったことはない。照れ臭いというのもあるけど、ちょっとだけ自信がなかった。多分、零那もオレのことを好きだと思ってくれていると思う。ただ、千明と瞬を友だちだと言ってあっさり納得した零那としては、本当に男女の友だちとして接しているのかもしれないとちょっとだけ思ったのだ。瞬に「告んないの?」なんて言っておいて、オレ自身はできないでいるなんてちょっと情けない感じもする。ただ、今の関係が続くのであれば、このままでいいかなと思う自分もいた。 そんなある日のこと。演劇部の練習時間で筋トレをした後、疲れたオレは汗をタオルで拭いて水を飲んでいた。千明として養成所で筋トレをやらされることはあったが、小学校の演劇クラブではここまでのトレーニングはなかった。小学校の演劇クラブは遊びの延長線上でしかないことを思い知った。 そんな時、「太一くん」と呼びかけがあり、振り向くと零那がいた。思わず疲れも吹き飛んでいった。零那の顔を見るだけで癒しになる。 一通り話してもう一度水を飲むと、零那は視線を外し、そのまま阿僧に話しかけた。どういう関係だと思って気になってそちらのほうを見ていると、急に瞬が「あーー!!」と大きい声をだした後に話しかけてくる。 「太一、こっちに来い。ちょっと話があるから」 「えっ? な、ちょっと何でだよ…」 「いいから早く」 仕方なく瞬についていって練習場所から離れていき、渡り廊下まできたところで瞬はようやく口を開いた。 「前に太一、昔見たミュージカルの女の子が初恋だって言ってたよな?」 急に何だと思った。ちょっと言い回しが気になったけど、そのまま返答する。 「そうだよ。あの時、零那の演技を見て好きになった」 「今でも好きか?」 いったい何を言いたいのか分からなかった。その要領を得ない質問に少しイライラする。そんなの決まっている。 「今でもだよ。オレは零那のことが好きだ」 「ならいいよ。話はそれだけだ」 瞬はそういうと、練習場所に向かって歩いて行った。 なんじゃそりゃ。本当、何が言いたいのかも分からなかった。余計なお世話だ。「お前のほうこそ、阿僧が好きなら早く告白しろ」とでも言おうと思ったが、ケンカになりそうだったのでやめておいた。 それから数日がすぎ、テスト期間が近づくと部活は休みになった。普段、瞬と帰っているが、この日は零那と帰ろうと思い、下駄箱で合流して並んで帰ることにした。 何を話そうと思い、零那が出演していたアニメ『ペンタゴン娘』が最近、最終回になったのでその話をしようと思った。このアニメは数学に関する話のアニメだったけど、何分、下ネタが多く、思春期の自分は見ているだけで少し恥ずかしくなった。特に、零那が言ったセリフ、「円周の公式は、2πr(にぱいあーる)というのではなくて、ππr(ぱいぱいあーる)と言うほうが、スキ」というセリフはとても恥ずかしくなった。いったい何を思って女子中学生にそんなセリフを言わせたのだと思う。ただ、そんなキャラであっても零那らしい表現力が伝わってきたのでとてもよかった。 そんな話をしている中で、零那は尋ねてきた。 「そういえば、太一くん、前にあたしに憧れて千明ちゃんとして声優になったって言ってくれたよね? 何の芝居だったの?」 あれ? 言ってなかったけ? と思い返す。そういわれてみれば、言ってなかったような気もする。 「ああ。そういえば言ってなかったっけ。『点と線との阿弥陀くじ』だよ。あのミュージカル本当良かった。あれで零那を見てオレは憧れた。今思うと、初恋だったのかなって思う。って、改めて言うと、ちょっと照れ臭いけど…」 自分で言ってて恥ずかしくなる。こんなの、告白してるみたいなもんじゃないかと。横を見ると、零那も少し照れているようだ。ふと、先日瞬に言われたことを思い出す。「今でも好きか?」。あれはもしかしたら、ちゃんと好きと伝えろということなのかもしれない。瞬も、直接言ったら「お前が言うな」と言われると思って言えなかったのか。でも、確かにちゃんと伝えた方がいいかもしれない。今なら言えるんじゃないかと思って口を開きかけた時、零那が先に話し出した。 「そういえば、聞いてるかもしれないけど……」 そう話し始めて続けた零那の言葉にオレは思わず足を止めた。 「あのミュージカルってあたしと百花ちゃんとのダブルキャストだったんだ。」 その後、何を言ってたのか分からない。胸の中でモヤが渦巻いているような感じだ。ふと、幼少期に見た女の子の顔を思い返す。オレの初恋の女の子阿僧にそっくりな女の子だ。 「どうしたの?」 前を歩いていた零那が振り返ってそう言った。 「いや、なんでもない。そっか。そうだよね。あのミュージカルは本当よかったよ…」 そんな的を得ないことしか言えなかった。 もし、オレが昔見た女の子が阿僧だとすると、オレの初恋は阿僧だということになる。そう考えると胸がモヤモヤした。 ずっと初恋相手は零那だと思って接してきた。いったい、どこで間違えたんだ。そうだ、あの時だ。瞬が『点と線との阿弥陀くじ』のファンページを探してくれた時、そこで零那の名前を見たんだ。役名については覚えていたオレはその名前を見て零那だと思った。ダブルキャストなんて思ってなかった。あのサイトをもう少し見てみると阿僧の名前もあるのかもしれない。 それから、休み時間には零那に会いにいけなくなった。こんなモヤモヤな気持ちを抱えてうまく話せる自信がない。実際、零那から話しかけてくれた時も、自分で分かるほどぎこちなかった。役者としてまだまだ三流だと思い知る。 「十河くん」 休み時間中、自分の席でボーっとしていると、阿僧に呼びかけられてドキッとした。一瞬、昔見たミュージカルの女の子と顔が重なる。 「大丈夫? 何か最近、元気なさそうだけど…」 「そ…そうかな? いや、大丈夫だよ全然平気」 「それならよかった。さっき部長とすれ違って伝言を頼まれたの。夏に区民ホールでやる劇にでてほしいって」 「えっ! 本当に!?」 この学校の演劇部では、新入生歓迎会や文化祭など、年4回ほど劇をするらしい。その中の一つが学校外で夏にやる劇だ。演劇部員の人数は結構な数なので、1年生の自分がでることになるとは思ってなかった。うれしくて思わず笑みがこぼれる。 「やっぱりすごいなー、十河くんは。そうそう、京極くんも出演予定みたい。久々に十河くんと京極くんの演技が見れると思うとあたしもうれしいな。」 前に、阿僧に「きっと、また演劇やるよ! 瞬と一緒に!」と言ったのを思い出す。オレも瞬とまた演劇できると思うとうれしい。 「そうだね。オレも久々に舞台にでれるのは楽しみだな」 「二人とも演技うまいもんね。あたしなんて、まだまだだなーって思う」 「そんなことないよ。」 阿僧だって昔…。そう言おうとしたらチャイムの音が鳴って、阿僧は自分の席に戻っていった。一瞬、廊下に視線をやると、零那が去っていくのが見えた。 やっぱり、何か零那と話したほうがいいのだろうかと悩む。いやでも、話すったって何を話せばいいんだ。「オレがあこがれてたのは零那じゃなくて阿僧だったみたい…」なんて言えるわけない。そんなこと言ったら零那が悲しむだけだ。 むしろ、阿僧のほうに言うべきか。千明として声優になったのは阿僧がきっかけって…。いや、それも何か違う気がする。 そんなある日の放課後、阿僧に二人で話したいことがあるから屋上に来てほしいと言われ、後を着いていった。心臓がドキドキと鳴ってるのが分かる。いったい、二人きりで話すことってなんなんだ。もしかして告白だろうか。2年前に阿僧に告白されたことを思い出す。あの時は零那のことが気になってるといって振ったのだった。でも、オレの初恋は零那じゃなくて阿僧だ。もしあの時、そのことに気づいていたら、今頃、阿僧と付き合っていたかもしれない。 屋上につづく扉を開けて、外にでる。 「よかった。雨やんでるみたい」 阿僧が言った。曇り空だったけど、雨は降ってない。 「えっと、それで、今日話って……」 「うん。ちょっとね。話しておきたいことがあって…」 阿僧はそう言うと、一度、深呼吸をして続けた。 「あたしね、昔、零那ちゃんとダブルキャストでミュージカルにでたことがあるんだ。『点と線との阿弥陀くじ』っていうミュージカル」 心臓の鼓動がさらに速くなった。まさか、阿僧のほうからその話をしてくると思わなかった。 「あの時の零那ちゃんはすごかったよ。幼かったあたしでも演技力が高いって分かった。あたしは一生懸命、零那ちゃんの演技を真似しようとしていたけど、全然ダメ。舞台にでることは楽しかったよ。でも、あたしには無理だなって。見てるほうがいいなって思って、演劇を続けないことにしたんだ。」 阿僧は昔を思い出すように、そういった。零那の演技をみて、かなわないと思うのは自分にも経験があった。昔からそうだったのかと知る。 「ごめんね。衝突にこんな話。実は零那ちゃんから聞いたんだ…。そのミュージカルで見た女の子が…、十河くんの初恋だって」 これまた衝突な言葉だった。零那が、阿僧に、オレがミュージカルで見た女の子が初恋の子だということを伝えたという。 「あ…、うん…、そうだよ…。それが初恋だった…」 急に恥ずかしくなって顔が赤くなったのが分かった。初恋の人の前で初恋だというのだ。恥ずかしくないわけがない。 やっぱり、これは阿僧からの告白なのかもしれない。ただ、その後の阿僧の言葉はオレの予想とは違った。 「今でも?」 「えっ?」 「今でもその子のこと好き?」 衝突な質問に驚く。最近、同じことを瞬に聞かれた。 「今では…」 ふいに零那の顔が浮かぶ。笑顔の零那だ。 「違うよね? もしかしたら、十河くんが小さい時にみた女の子はあたしだったかもしれない…。でもね……、今の十河くんは零那ちゃんのことを大好きだってことは見てたら分かる。小学生の時、ホームルームが終わったら真っ先にでて零那ちゃんの家にむかってたんだよね。あの時の十河くんの気持ちは嘘だったの? ただの同情心からだったの?」 小学生の時、学校をでて急いで零那の家にいくと、零那が駆け寄ってきて耳元で「うれしい」とか「ありがと」と言っていたのを思い出す。その度に心臓がドキドキと高鳴ったし、うれしかった。 「中学になって一緒になって、よく一緒に話してたよね。二人ともすごい楽しそうだった。幸せそうだった。正直、それを見て胸が痛むこともあった。でもね、あたしは十河くんも零那ちゃんも好きなの。だから、そんな二人の関係を応援したいと本心で思ってる。そんなあたしの気持ちを、初恋が違う人だったという理由で、壊さないでほしい。今の自分の気持ちに正直になってほしい。零那ちゃんが大好きだっていうその気持ちに正直になってほしい!」 阿僧は叫ぶようにそう言った。思わず、零那との思い出がよみがえる。声がでなくても一生懸命に頑張る零那。なかなか声がでないで悔しそうにする零那。初めてまともに歌を歌いきれた時の嬉しそうな零那。演技の練習を楽しそうにやる零那。 「零那に…会いたい…」 思わず心の声が漏れた。零那のことを考えただけで、胸が苦しくなった。 「行ってあげて。零那ちゃんはさっき帰ったばかりみたいだから」 優しい声で阿僧が言った。オレがいかにひどいヤツかを思い知る。一度ならず、二度までも自分のことを好きと思ってくれる人に、零那の後押しをしてくれたのだ。 零那に会いに行こう。そう思ってすぐに、体の向きを変えて屋上の扉を開けた。ただ、最後に一言伝えておきたいと思ってそこで一度立ち止まり、振り返って阿僧にむかって叫んだ。 「阿僧は、もっと自信持ちなよ。オレが心動かされるぐらいの演技をしてたんだから!」 阿僧は予想外といったように驚いた顔になり、「うん。ありがとう!」と叫んだ。少し、泣いていたようにも思う。 オレは急いで階段を駆け下りた。靴を履き替える時間すらおしいので、靴を履き替えずに下駄箱を抜け、校門をでる。雨が降ってきたが、そんなこと気にしてる場合ではない。傘もささずにオレは走った。 零那がなぜオレが見たのは阿僧だと気づいたのか分からない。瞬から聞いたのかもしれない。瞬は知っているようだった。先日の話はそのうえでの忠告だったのだろう。 オレはバカだ。大バカ者だ。瞬や阿僧のいうとおりだ。初恋にばかり気を取られ、今の自分の気持ちをおろそかにしていた。でも、今ならはっきりと言える。オレは零那のことが好きだ。大好きだ。 零那の書く文字が好きだ。達筆な文字。読みやすく、思わず目に飛び込んでくるし、もっと読みたいと思える。 零那の演技が好きだ。その圧倒的な表現力は人を惹きつけて感動させる。思わず涙がこぼれそうになったのは一度だけではない。 零那の笑顔が好きだ。これほどまでに笑顔が似合う女の子はいるだろうかと思う。オレにとっては癒しだ。この笑顔を大切にしたいと思った。 零那の声が好きだ。その親しみのあるかわいい声はいつまでも聞いていたくなる。笑った声、楽しい声、悲しい声。全部、大好きだ。 オレは、零那のすべてが好きだ。大好きだ。 校門をでて、しばらく走っていると零那の背中が見えた。雨が降っているのに、傘もささずに歩いている。 「零那!!」 オレは咄嗟に叫んで、そのまま後ろから抱きついた。思ったより華奢な体だ。こんな小さな体で、あんなに素晴らしい表現ができているのかと思い知る。 「ごめん。今までちゃんと自分の気持ちを伝えてなかった。オレは零那のことが好きだ。これからもずっと一緒にいてほしい」 零那がどう思うか分からないが、自分の気持ちを伝えたくて仕方がなかった。 「だ…、だって…、太一くんの初恋は百花ちゃんだって…」 嗚咽をあげて零那はそう言った。零那を泣かせたのはオレだ。 「初恋なんて関係ない。今は零那が好きなんだよ。確かに、昔見たミュージカルの女の子が零那じゃなくて阿僧だって分かったときは動揺した。もし、最初から阿僧と分かっていたら、阿僧と付き合ってたかもしれないって思った。でも、2年前に零那と出会って、千明として一緒に仕事をして、中学で一緒に話した日々があって、その積み重ねがあったから好きになったんだ。それを無かったことになんてできないんだよ」 感情が高ぶっているのが分かる。抱いている腕も少し強くなった。このまま、離したくないとさえ思う。 雨はさらに強くなっていった。体が冷えていくのがわかる。 「あたしも…、」 零那はそこで一呼吸して続けた。 「あたしも、太一くんが好き」 それを聞いてオレは、零那を抱いている腕の強さを少しゆるめた。同時に、零那は抱きしめてるオレの手を握りしめる。 「千明ちゃんの声のする男の子と家の前で出会ってからずっと好き。少し目が合っただけなのに、ずっと顔を覚えていたんだよ。すぐには初恋だって気づかなかった。でも、千明ちゃんがその男の子だって気づいた時に、腑に落ちたの。あたしは千明ちゃんの声が好きなんだって。もちろん、今の太一くんの声はあの時とは違うけれども、親しみやすくて優しい声は変わってない。」 零那はゆっくりと抱いていたオレの腕をほどき、体ごと振り向いた。 「声だけじゃない。千明ちゃんが男の子だって気づいた時、今まで千明ちゃんがあたしにしてくれたことを思い出したの。ミュージカルのオーディションに誘ってくれた千明ちゃん。学校が終わるとすぐに家に来てくれた千明ちゃん。声のでないあたしのリハビリに付き合ってくれた千明ちゃん。一緒に劇の練習をした千明ちゃん。あたしの声が好きだって言ってくれた千明ちゃん。いつもいつも一緒にいてくれた。そんなの、男の子って分かったら、好きにならないなんて無理だよ。太一くんだってそう。休みになると会いに来てくれて、ご飯も一緒に食べて、一緒にお出かけもして…。その度にもっと好きになっていった…。でも…、でもでも太一くんはあたしじゃなくて百花ちゃんのことが好きなんだって思って…、だから応援しようと思ったのに、そう思った…のに、な…涙がが…あふ…れ…て…」 零那は嗚咽をあげながら続けざまにそういった。最後のほうはほとんど声になっていない。 オレは再び、零那を抱きしめた。今度は、正面からだ。千明だった時に、零那が駆け寄ってきて抱きしめたい衝動に襲われたのを思い出す。 「もう自分の気持ちに嘘はつかない。零那とずっと一緒にいたい。」 零那は顔をあげた。先ほどから泣き続けている。零那はそのまま、「ありがと」。そう言った。雨の音でかき消されてかすかに聞こえる声だった。 声が出なくなった零那が、初めて声をだそうとしていた時のことを思い出す。多分、オレはあの時、初恋の女の子と関係なく零那を好きになった。 今はその時と同じかもしれない。零那のためなら、オレはなんだってやろうと思う。 それから、オレと零那は前と同じように、いや、前以上に親交を深めていった。 「瞬もありがとな。多分、いろいろ気を気をつかわせちゃったと思うけど、瞬と阿僧の言葉のおかげで、よりを戻せた」 部活が終わって制服に着替えながら、横にいる瞬にそう言った。 「オレは何もしてねーよ。むしろ、オレも毛利に太一のこと話過ぎたって反省してる。言い方も悪かったなって。一応、毛利に話した後、今の太一は毛利のこと好きだから大丈夫って言ったけど、意気消沈してたっぽいから耳に入ってなかったのかもなって思う」 「いや、瞬は悪くないよ。確かに零那を泣かせることになったけど、それはオレが初恋が零那じゃないと気づいて動揺したせいだし。むしろ、そのおかげで零那にたいしての正直な自分の思いに気づいたし、伝えることができた。零那とずっと一緒にいたいってそう思った」 瞬はオレのその言葉を聞いて一度ため息をついた後に口を開いた。 「新婚ホヤホヤでいっしょにいたいてのはわかるけど、ラブラブすんのもほどほどにな。」 入学式の日に、オレが瞬に言った言葉だ。正直、苦笑するしかない。 「そーいえばさ…」 瞬はそう言って、カバンの中に手を突っ込んだ。 「事務所から渡されたんだけど、お前にやるよ」 そう言って瞬はA4の紙の資料を手渡した。紙には、ミュージカルのオーディション要項が書いてある。 「今日練習してて思ったけど、おまえの実力はこんな中学の演劇部だけで終わらせるのはもったいない。また、やってみないか?」 「瞬は応募するのか?」 「オレはでない。歌もたいしてうまくないし、芝居も演劇部レベルから抜け出せていない。やり直しの聞くドラマやアフレコならギリできるけど、お金を払って見に来てくれる客がたくさん見ている中でやる勇気も、今のオレにはない。でも、太一の実力なら十分やっていける。というより、また仕事として演技をしてほしいと思ってる。そしていつかまた、一緒に仕事がしたいと思う」 瞬のその言葉にオレは照れた。そんなふうに思ってるなんて思いもしなかった。 千明としてデビューする前は、太一として芸能界に入ろうと思ったこともあった。でも、千明としてデビューした時、オレにはこの声が武器になるんだと気づいた。ただ、その声を失って、つまり武器を失った時には、太一としてデビューしなおすなんて考えもしなかった。 でも、零那だって、昔と声が変わってしまったからといってあきらめてたけど、必死に努力して立ち上がった。もちろん、昔のような声がでてるわけではないだろうけど、今の声は今の声で、活かしている。オレだって、今のこの声ならではの演技だってできるかもしれない。 「ありがとう。やってみるよ」 着替え終わったオレは、オーディション要項を手に帰り支度をして校舎をでた。瞬は鍵を返しに職員室に行ったので、校舎前で待つことにする。先日の大雨がウソだったかのように、今日は晴れ晴れとしていた。 オレはもう一度、オーディション要項を見た。ミュージカルの概要には学園もののミュージカルとある。10代の男女を募集しているという。はっきりと書かれてはないが、内容からしてシングルキャストだ。 そうだ。零那も誘ってみよう。『千夜一夜物語』の時には、ダブルキャストだったのでほとんど一緒の舞台にはたてていない。今度こそ一緒に舞台で共演したい。 そんなふうに思っていると、「太一くん!」と声がした。そこには、息をあげている零那がそこにいた。どうやら、走ってきたようだ。今日は、アニメの台本をとりに事務所にいくと言っていた。どうしてまた学校に戻ってきたんだと思ったら、零那は紙を掲げてオレに見せた。 「さっき事務所でもらったの! ミュージカルのオーディション! 太一くんと一緒に受けたい!」 その紙は、先ほどオレが瞬からもらったオーディション要項と同じことが書かれてあった。 ふいに笑いが漏れる。オレもその紙を零那に向けて差し出す。 「オレも同じこと考えてたとこ!」 家に帰ったオレは机の棚にオーディション募集要項をいれた。 その棚には一通のハガキがある。零那が初めて送ってくれたハガキ。このハガキがあったから、オレは零那に出会うことができた。 生涯、このハガキを大事に持っていようと思う。少女少年VIIの終わり方って初めて読んだとき、すごいもやもやしたんですよね。初恋の相手は実は百花だったんじゃないかというような終わり方なうえに、どうも百花も零那も太一と同じ中学校に通うことになりそうという(実際には、零那が同じ中学かどうかの記述はないのですが、状況的にそうなのかなと思ってこの小説でも同じ学校に通うという設定にしました)。
この3人が同じ中学ってなると、太一の初恋の相手は百花だと知るのも時間の問題だろうし、そうなるとギクシャクするだろうなとずっと思ってたんですよね。続きがあるとしたら、どういう展開なら自分は納得できるだろうかと考えたうえで書いた小説です。
なので、一番書きたいのは中学入学以降の話ですが、本編の時系列の零那視点やオーディションを受けて合格するまでも書いてみようと思って書いてみました。
ただ、このへんは一人のファンの自分の解釈であって、人それぞれ解釈は違うでしょうし、やぶうち優先生の考えももちろん違っていると思います。
ところでこの小説を書いてる時に、ダブルキャストの実例を調べてみると、同じ役だとすごい似てるんですよね。ということは、零那が百花に似せて演じていた可能性もあるわけで、ということはやっぱり太一が見た初恋の子は零那なんじゃないかと思いました。そう考えると、太一が百花の名前を、初恋の子と違う気がすると思ったのにも、瞬が零那を調べて百花似の女の子の写真がでてくるのも説明がつくんですよね……。
多分、太一の初恋の女の子が零那だったと最初から思っていたら、瞬が一生懸命、太一に初恋の相手が百花だと分からないようにするコメディー小説を書いたと思います