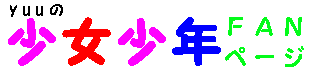白鳥つぐみ、青葉のぞみ編~のぞみのデビュー、つぐみの引退~
藍沙のファン(ストーカー)に白鳥つぐみが男だとバレそうになった時から数か月がたった。季節は春。 允たちは中学生となったが、声変わりのしていない允は白鳥つぐみの芸名で、芸能活動を続けていた。 そんな中、つぐみ姿の允は、とあるビルで少し浮かない表情をしている。 「去年は藍沙と一緒だったのになぁ・・・」 1年前の今日、つぐみは藍沙と出演することになるソフトクリームのCMのオーディションを受けた。そのオーディションの晴れて合格して、デビューしたのだ。 しかし、今年は藍沙は出演しない。制作者が、昨年藍沙に励ましてもらったつぐみが、逆に今年は励ます側にしようと考えたらしい。 そして今日も同じ商品のCMのオーディションが行われようとしている。 さらに今回は前回とは違って、出演が決定済みのつぐみもオーディションに演技者として参加しなければならないという。 「めんどくさいなぁ」 とはいっても仕事は仕事。稼ぎ時はもうすぐ終わるだろうから、とつぐみは心機一転して気合いをいれた。その時だ。 「つぐみ、つぐみ」 村崎ツトムの呼ぶ声がしてつぐみは後ろを振り向いた。 村崎さんの隣には、小学生に見える、緑のツインテールの女の子が立っている。 「こちら、今日のオーディションを受けることになった青葉のぞみちゃん」 「青葉のぞみです。本日はよろしくお願いします」 青葉のぞみと名乗るその女の子は幼い容姿とは裏腹に、丁寧に深々とお辞儀をして挨拶をした。 うへぇ。しっかりしてるなぁ。 と感心しながら、つぐみも「こちらこそ、よろしくね」と、営業スマイルで挨拶を返した。 「では、オーディションに参加する人は今から簡単に説明をしますので、会場に入ってください」 と、オーディション会場となる場所から男の声がした。 「じゃあ、君は先に会場入りね」 「はい」 そう言ってのぞみは駆け足で会場に向かって行った。 つぐみは、のぞみが会場に入っていくところを見届け、村崎さんに話しかけた。 「あんな子うちの事務所にいましたっけ?」 「いや、最近うちの事務所に応募してきてね。しっかりしてるし、なかなかよさそうだと思ってね。とりあえず、このオーディションに出させてみようとおもったわけ」 「ふぅん。何年生なんですか?」 「確か、今年から小学4年生だったかな」 「えっ!? 小4!」 つぐみ(允)は自分が小学4年生の時を思い出していた。 確か、その頃はBMチョコにはまりはじめたころで、まだ雪火にも会ってなかったし、女装もしていなかった。 一つ言えるのは、自分はあそこまでしっかりしてなかった。ということだ。 「オレも負けてられないなぁ」 そんなことを思いながら、つぐみも会場に入ることにした。 のぞみは緊張していた。 もとはと言えば昨年のつぐみの活躍を見て憧れた世界で、まさか最初のデビューのチャンスがつぐみとの共演とは思っていなかったようだ。 先ほど、つぐみに挨拶をしたものの、はたしてあれでよかったのか少し不安に思っている。 もう少し何か言った方がよかったんじゃないか。年齢とか趣味とか、後はそう、つぐみに憧れてこの世界に入ったということとか。 とはいっても、それは終わったこと。今は、説明員の言っていることをちゃんと聞くことにした。 内容は簡単だった。審査は呼ばれた人から順番にやるということ。合格者は後日発表になるということ。そして肝心の審査内容は、 つぐみが「元気、出して」と言ってソフトクリームを渡してくるので、そのあとの演技をアドリブでやるとのことだった。時間はCMのとおり30秒。 「何だ。簡単だね」 「去年のつぐみさんのようにやればいいんだよね」 のぞみの耳に、回りの女の子のそんな声が入ってきた。 違う。多分、そんなんじゃない。もしそうだとしたら、アドリブなんてことにしないはずだ。 のぞみはそう思った。だが、どう演じればいいか思いついたわけではなかった。 その後すぐ、審査員の人も会場入りし、オーディションが始まった。 呼ばれた女の子から順番に演じていく。 やっぱり、どこか昨年のつぐみを思い起こさせる演技をしている人が多い。わざとではなく、その記憶に引っ張られている人もいるのかもしれない。 昨年のつぐみのようにやってない人もいたけれども、インパクトがない。ただ、おいしそうに食べてるだけだ。 「次、青葉のぞみさん」 「はい」 のぞみは元気よく返事をして立ち上がり、考えた。 このオーディションで見られるのはつぐみさんの真似事なんかじゃない。ましてや、ただたんにおいしそうに食べれるかということではない。 そんなんじゃインパクトなんてでない。 「よろしくお願いします。」 「元気、出して」 つぐみがそう言いながら、切ない表情をしているのぞみにソフトクリームを差し出す。 のぞみは差し出されたソフトクリームを一口食べるとすぐに驚くように嬉しそうな表情になったが、またすぐに切ない表情に戻った。 そして、今度は睨みつけるようにつぐみのほうを見て、ソフトクリームを差し出し、のぞみは言った。 「一緒に食べてくれなきゃ元気になれない」 つぐみは少し動揺していた。 スタッフに言われていることは、最初のソフトクリームを渡す演技だけでのみ、相手が話しかけてきた場合、応対をするべきかどうなのかどうかと。 考えている暇などなかった。つぐみはすぐに泣く演技をするやいなや、すぐに明るい表情となってそのソフトクリームを食べた。 そして、頬にクリームがつくと、投げキッスをするようにそのクリームをとった。 それは昨年、つぐみがオーディションでやった演技だった。 「いやぁ、またつぐみのあの演技が見れるなんて思わなかったよ」 「今回の泣きはうれし泣きだったね」 オーディションが終了してスタッフたちはつぐみにたいしてそのように話していた。 「あはは。何か、あの子見てると対抗意識がでちゃったみたいで」 「そうか。なら、決まりだな」 CMは後日、昨年と同じように北海道で撮影することになった。ホテルの部屋は昨年と同じく、共演者同士が同じ部屋。 とは言っても、つぐみは昨年と違い、女の子と一緒の部屋だからといって、気まずかったり緊張したりしているわけではなかった。 女の子とは言っても相手は3歳も年下で、まだ幼い。さらに、この1年で一緒に仕事をすることになる女の子と控室などで一緒になることも多かったので、女の子と一緒の部屋になることはかなり慣れていた。 対して、のぞみのほうは少し緊張していた。同じ事務所の先輩で、憧れのつぐみと一緒の部屋というのだから無理もないのかもしれない。 「そんなに緊張しなくて大丈夫だよ。何もしないし。テレビでも見る? と言っても、この時間は面白そうな番組やってないんだよねぇ。そういえば、北海道ってNHKが3チャンネルで、12チャンは教育なんだよ」 「あの、つぐみさん」 一人でいろいろ話していたつぐみに対して、のぞみが話しかけてきた。 「どうしたの? 何か見たいものでもある?」 「いえ、そうじゃないんです。あたしが芸能界に入ろうと思った理由について話させてください」 ふと、つぐみは自分がこの世界に入った理由を思い出した。 確か、BMチョコを百万個以上買えるぐらい稼げるというお金に目がくらんで、入ろうと決意したんだ。と。 本当、あのときは子どもだったなぁ。と、つぐみは懐かしく思った。 「あたし、つぐみさんに憧れてこの世界に入ったんです」 つぐみは胸がドキッとなるのを感じた。 「テレビや雑誌に載っているつぐみさんに、なんだかすごく生き生きして輝いているように感じて・・・。あたしもあんな風になりたいとと憧れて、この世界に入ろうと思ったんです。だから今回、つぐみさんと一緒に仕事ができるのがうれしくて夢みたいで・・・」 つぐみは照れくさがった。 村崎さんから『アイドルは夢を与える仕事』ということはよく言われてきたけれども、まさか本当に自分がここまで人に影響を与える存在になっているなんて。と、思いもよらなかったようだ。 「そ、そっか。なんだか照れくさいなぁ。ありがとう。」 そのつぐみの言葉にのぞみも微笑んだ。先ほどまで少し緊張して強張った表情だったけれども、笑うとすごくかわいい。 「そうだ。分からないことがあったら何でも聞いて。そうだ。浴衣はね、左前じゃなくて右前に着るんだよ。右前というのは、皮膚に近い方が右ということね。それと、お風呂のシャワーカーテンなんだけど・・・」 「はい。バスタブの中に入れてシャワー浴びるんですよね。ここに来る前に、ホテルでのマナーを勉強してきました」 その言葉につぐみは少しショックを受けた。 それから数か月たったある日のこと。 ソフトクリームのCMの撮影以来、のぞみとつぐみはたびたび一緒の仕事をすることはあったが、すぐにのぞみは単独で活躍するようになった。 その日のぞみは、『小学四年生』のインタビューが終わり、今はその雑誌に掲載するための写真の撮影を行うところであった。 「あら~。カワイイ子ね~。気に入ったわ~」 カメラマンの篠原先生がのぞみにたいしてそう言うが、対してのぞみは篠原先生に対して、気持ち悪いという印象を抱いた。 ただでさえ、このところ体調が思わしくないのに、こんな気持ち悪い人がカメラマンだなんて・・・。と。 その後、撮影が始まったが、あまり順調にすすまず、何度かの篠原先生の撮り直しの要求があり、予定より少し時間をオーバーして撮影は終了した。 すぐに、撮影した写真をのぞみは見てみたが、全然かわいく映っているようには見えなかった。 昔から、趣味でどういう角度で撮ればかわいく映るか研究してきたのぞみにとって、それをいちいちケチをつけられたことも不満だった。 「あ~。ダメだ。なんだかくらくらする」 体調の優れないのぞみは、トイレに入っていった。 このところ、のぞみはお腹のあたりが痛くなることがよくあり、今日もお腹が痛いから休みたいと村崎さんに言うと、「のぞみはプロなんだから・・・」と何かいろいろ言われて休ませてもらえなかった。 のぞみはパンツを降ろした。 いっぽう、つぐみはバラエティー番組の収録で頂いた弁当を食べながらテレビを見ていた。 番組はCMに代わり、のぞみが単独で出ているCMが流れる。 「のぞみちゃん、急上昇で人気でてきてるなぁ・・・。このままいくと追い抜かれそうだ」 つぐみが先日、スタイリストの小町さんに聞いたところ、人一番真面目で熱心に仕事をしているとのことだった。 弁当を食べ終わったつぐみは、尿意からトイレにいくことにした。 去年の春には女子トイレに入ることにたいして抵抗があったものの、今では全く抵抗なく普通に女子トイレに入ることができるようになっている。 トイレに入ってみると、個室の一つはすでに誰かが入っており、つぐみはその隣の個室で尿を足すことにした。 つぐみが尿を足し終わって個室からでても、まだ隣の個室に入っている人はでてきていないようだったが、つぐみは気にせず洗面台で手を洗っていた。 その時、先ほどまで閉まっていた個室の扉が開いた。 中からでてきたのはのぞみであった。 「あっ! のぞみちゃん久しぶり~。元気にし・・・」 と、つぐみはのぞみに言いかけてやめた。どう見ても、その時ののぞみの表情は元気に見えなかったからだ。 「ど、どうしたののぞみちゃん? 具合悪い?」 「つぐみさん・・・」 のぞみはつぐみの顔を見つめ、少し安心した表情になった。 「あの、つぐみさん。前に分からないことがあったら何でも聞いてって言ってくれましたよね・・・」 「うん。もちろん。」 「あたし、初めてでこういう時どうしたらいいか分からなくて・・・」 のぞみは、一通りの経緯を話始めた。 「げっ・・・月経・・・!?」 一通りのぞみから話をうけたつぐみは驚いた。 まだ小学4年生なのに、月経が来るのかと。 ただ、つぐみは男なので、勝手が分からない。 「ごめん、のぞみちゃん。あたしは来ない・・・」じゃないや「まだ、来てなくて・・・。」 つぐみはとっさに携帯電話を取り出した。のぞみが近くにいるなら、多分近くにのぞみのスタイリストの小町さんがいるはずだと考えたのだ。 つぐみの予想通り、小町さんは同じビル内にいて、トイレに呼んでのぞみを迎えにきてもらった。 小町さんに付き添われながら去っていくのぞみの後姿をつぐみは見て思う。 「情けないなオレ」 本当に後輩が困っているときに何もしてあげることができない。 そして、今まで女の方が得だと思って女のフリをしていた自分に、つぐみは罪悪感を覚えた。 「得ばっかりじゃないんだよな・・・」 つぐみはうつむき加減で控室に戻っていく。 その途中のことだった。 「ん゛・・・ごほっ。」 つぐみはその時、のどに違和感を覚えた。 「俺ものぞみちゃんと同じで、身体は否応なしに大人になろうとしてるのかな・・・」 つぐみは後ろを振り向き、のぞみが去った方向を見ながらそうつぶやいた。 数週間後、久々につぐみとのぞみは一緒の仕事となった。 「先日は、お騒がせしてすみませんでした」 のぞみは、つぐみにあうなりそう言って謝った。 「ううん。こっちのほうこそごめんね。頼りになれなくて・・・」 「そんなことありません。あたしは動揺していて、小町さんを呼ぶなんて思いつきませんでした」 「そっか・・・」 つぐみは頭を少し下げてのぞみと話した。ふとつぐみは、出会ったときはこんなに身長差あったかな・・・と思う。 「じゃあ、つぐみ、のぞみ、スタンバイして」 「はい゛・・・ゴホッゴホ」 スタッフの呼びかけに返事をしようとしたものの、つぐみは思わず喉をつまらせてしまった。 あれからつぐみには、つぐみの声、つまり女の子のような声を出そうとするとよく咳き込むことがあった。 「大丈夫ですか? つぐみさん」 「うん大丈夫。行こうか」 つぐみとのぞみはスタンバイした。 今日はあるティーン雑誌の撮影である。今回のテーマは『姉妹でおでかけ』 だいぶなれてきたけれど、フラッシュはまぶしい。そう、つぐみは思った。 「いいね。そうそう。本当の姉妹みたいだよ」 カメラマンにそういわれて、のぞみは照れていた。 そして、撮影は順調に進み、予定時間より早く終了し、つぐみとのぞみは撮影した写真を見た後控室に戻っていった。 「やっぱり、カメラマンによって良し悪しに差がでますね。自分でいうのもなんですけど、さっきの写真、すごく可愛くとれていたように思います」 「そうだね」 控室に戻りながら、つぐみとのぞみは二人でそんな会話をしていた。 「ねえのぞみちゃん。村崎さんから聞いたよ。今度ファンクラブやるんだってね」 「はい。あたしもだいぶ人気でてきたかなって思います。つぐみさんほどじゃないですけど」 「そっか。でも、のぞみちゃんにはあたしよりもずっとずっと人気になってほしいんだ」 「えっ?」 のぞみはその言葉で立ち止まり、それに少し遅れてつぐみも立ち止まった。 「のぞみちゃんには日本で一番のアイドルになってほしい。できる?」 しばしの沈黙。 のぞみにはなぜつぐみが突然そんなことを言ってくるのかが分からなかった。でも、期待してもらえてるらしいと思ったのぞみは、元気に返事をした。 「はい。がんばります」 「ならよかった。じゃああたし控室ここだから。じゃあね」 「お疲れ様です」 こうして允は、つぐみとして最後の仕事を終えた。 「い・・・引退・・・!?」 先日のつぐみとの撮影の日から1週間がたち、のぞみは控室にあったスポーツ新聞を見ている。 そこにはでかでかと『白鳥つぐみ 電撃引退』と書かれていた。 のぞみがその新聞記事を読み進めていると、汗だくになった村崎さんが入ってきた。 「いやぁ。大変だったよ。マスコミに囲まれちゃって」 のぞみはすぐさま、新聞を村崎さんに見せて問い詰めた。 「どういうことですかこれ? つぐみさんが突然引退って!」 村崎さんはたじろいだ。 「ま、まあまあ、のぞみまでマスコミと同じようなこと言わないで・・・。ちょっと体調不良でね。学業にも専念したいって」 嘘だ。村崎さんの言葉に対して、のぞみはそう思った。こないだ会ったときだって、少し喉の調子がおかしかったが、とても急に引退をするほどの体調不良には見えなかったからだ。 でも、だからといって急に引退する理由が思いつくわけでもなかった。 「それはそうと、今日は小学四年生の撮影だよ。さあ急いで」 「なっ! 小学四年生の撮影の仕事はもうやめてほしいって前に言ったじゃないですか!!」 「そんなワガママが通用する世界じゃないんだよ。のぞみだってもう立派なプロなんだから」 のぞみは歯を食いしばった。 プロって何? 月経で辛い時も、嫌な仕事でもやることがプロなの? じゃあなんでつぐみさんは急に辞めたの? ワガママで辞めたんじゃないの・・・。 そんな風にのぞみは思った。 ふと、のぞみが村崎さんを見てみると、篠原先生と打ち合わせてをしていて、こちらを見ていないことに気付いた。 逃げよう のぞみはそう思うや否や、駆け足で飛び出した。 それからというもの、のぞみに脱走癖がついてしまい、時々仕事場から逃げ出すようになった。 最初のころは、逃げてもすぐに村崎さんに追いつかれ、連れ戻されることがよくあったものの、男装して脱走することにより、見つかりにくくなっていった。 そしてその日ものぞみは変装して村崎さんから逃げているところであった。 が、後ろから追いかけてくる村崎さんを気にし過ぎて、誰かとぶつかってしまった。 のぞみはそのぶつかった子の顔を見て驚いた。 まるで、鏡でもあるかのように、現在の男装したのぞみの姿にそっくりだったからだ。 ただ、そんなこと気にしていられないと、のぞみはぶつかった反動で少しずれたウィッグを抑えながら近くの本屋に入っていった。 「ビックリしたぁ。まさか、あたしの男装姿にそっくりな男の子がいるなんて・・・」 のぞみはそうつぶやくと、怪しまれないように外から見えない位置に移動した。その時だった。 「あっ! のぞみちゃん写真集出したんだ!」 男のそんな声が聞こえてきてのぞみはそちらに視線をやった。そこには近くの中学校の制服姿の二人の男の子が二人たっていた。 「この子のファンなのか?」 「まあ、そんなところかな。それに、俺はもう卒業したけど、大事な後輩だしさ」 卒業や後輩という単語から、小学校の先輩なのだろうかとのぞみは考えた。だけど、のぞみにはその男の子に見覚えがなかった。 すると、のぞみがずっとその男の子のほうに視線をやってたからか、その男の子とのぞみの目があった。 そして、のぞみは急に気恥ずかしくなり、本屋から駆け足で飛び出していった。 允は先ほど目があった男の子が、急に本屋に飛び出していったので、思わず目でおいかけていた。 「どうしたんだよ允」 雪火が允にそう聞いた。 「いや、のぞみちゃんがんばってるなって。このまま、つぐみなんか世間に忘れられるぐらい、人気になってくれたらうれしいんだけどね」 允はのぞみの写真集を手に、レジに並んだ。作品を超えた、クロスオーバー作品を書いてみました。
こんな小説を書きましたが、のぞみはもっと前から芸能界に入っていると思われます。
そう思われる記述がいくつかあるので(VIのP.47ののぞみの台詞「こっちは何年もやっててベストな角度だって研究しつくしてるのに」等。今回の小説では趣味でやってたということにした)