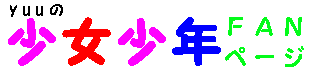毛利零那編~0と1の間~前編
あたしが、初めて千明ちゃんの声を聞いたのは何気なくつけていたラジオからだった。
声が出なくなってから不登校となったあたしは、勉強だけは遅れないようにするようにしており、同時にラジオを流していた。普段なら、どんな声かどころか、何を喋っているかさえ意識していなかったけど、その時は違った。
「みなさん、こんにちはーーっ!!」
夜の放送だというのに「こんにちは」から始まったそのラジオは、第1回の放送ということで公開録音で行われているとのことだった。
高くてかわいくて透き通ったような女の子の声。聞いているだけで心地よくなれる声だった。あたしもこんな声だったら、無理して高い声をだそうとせずに声がでなくなるようなこともなかっただろうと思った。
それから、あたしはそのラジオ、『千明の不可思議アイランド』を毎週かかさず聴くようになった。普段はラジオは流し聞きしているけど、このラジオだけは特別。勉強の手も止めて聞き入っていた。
特に『お悩み相談室』のコーナーが好きだった。他愛もない日常のお悩みを、等身大に親身になって考えて答えていく千明ちゃんの声にあたしは惹かれていった。
「あたしも何かだそうかな」
ふと、そう思ってハガキを手に取って書き始めた。字がキレイなほうが読んでくれるかなと思い、できるだけ丁寧な字を心がける。幸い、声がでなくなってから文字でのコミュニケーションが多くなったということもあり、キレイな字を書けるようになっていた。
『こんにちは。初めまして。』
そこまで書いてふと考えた。お悩み相談室だから悩みを書く必要がある。
悩みが無いわけではない。引きこもりだったり声がでなかったりするのは、確かに悩みかもしれない。でも、他人から見たら治したほうがいいと思われるかもしれないけど、今のあたしにとってそれは解決したい問題ではないと思えた。
だいいち、このラジオでそんな悩みはあまりにも場違いだ。恋愛相談とか友だちと仲直りしたいとか、他愛もない日常の悩みがこのラジオにはあっている。だけど、不登校のあたしにそんな悩みはない。
だから、そこでハガキをだすのはやめておこうということも考えた。ただ、なぜかは分からないけど、何か書いて送りたい。千明ちゃんにあたしのハガキを読んでもらいたいと思った。
多分、ハガキ代がもったいないからだろうと一人で納得し、ラジオの感想だけ書いて送った。
ただの感想なので、ラジオで読まれるとは思っていない。ただ、ハガキの選別をしているときに目に入って読んでくれるとうれしいなと思った。多分、もうハガキを送ることは無い。そう思っていた。
「みなさん、こんばんは、万丈千明です。今週も『千明の不可思議アイランド』の時間がやってきました!」
いつもと同じようにラジオが始まった。ただ、その日はいつもと違った。
「今日は最初にラジオ局に届いたハガキを紹介します。」
今まで最初にハガキを紹介することなんてなかったのに、今回はハガキを紹介するという。でも、別に変なことだとは思わなかった。普段、最初にオープニングトークとして最近あったできごとなんかを話すことは多い。多分、今日はハガキの内容とからめて話すのだろう。そう思っていた。
「神奈川県のレイナちゃん!」
「レイナ」と名前が聞こえて一瞬、心臓が跳ね上がった。でも、まさか自分ではないだろうと思った。「レイナ」なんて名前は珍しくもないし、あたしはペンネームすら書いていない。しかし、その後、読み上げられた内容はまさしくあたしが送ったハガキの内容だった。
「零那ちゃんありがとう! こうやって思ってもらえるなんてうれしいな。また、おハガキお待ちしています! では、コーナーのほうにいってみよー!」
信じられないと思うと同時に、笑みがこぼれた。うれしい、すごくうれしい。「零那ちゃん」って呼んでくれた。まさか、ラジオで読んでくれるとは思っていなかった。
「また、おハガキお待ちしています!」と言っていたのを思い出し、あたしはすぐにまたハガキを手に取った。まずは「読んでくれてありがとうございます。」かなといろいろ考えを巡らせた。
それから数週間がすぎた。
その頃のあたしは、声がでないのは精神的な理由からだということで、心療科のクリニックに通わされていた。
ただ、あたしはクリニックに行くのは嫌だった。無理やり心の中を覗かれるような気もするし、時には的外れだと思うことを言われることもある。
もうすぐでクリニックの時間だ。また、無理やり連れていかれるのは目に見えている。
あたしはそっと、家を抜け出すことにした。玄関にでて靴を履き、ドアを開ける。ドアを開ける音でママに気づかれてしまったけど、走れば大丈夫。あたしは、急いで家から離れようとした。
ふと、家の前で棒立ちになっている子が目に入った。一瞬気になったものの、気にしている場合ではないとそのまま離れようとした。
「きみ、毛利零那…さん?」
聞き覚えのある声にあたしは思わず立ち止まって振り返った。その声はまさに、毎週聴いている千明ちゃんの声だった。
その子は、男の子か、ボーイッシュな雰囲気の女の子に見えた。
「けっしてあやしー者じゃっ…! オ、オレ、きみのファンで…。」
一人称が「オレ」からして、どうやら男の子らしい。不思議に思いながらも、あたしはその場を離れた。
ただ、どうにもその男の子が気になって仕方がなかった。夜になって家に帰ってきてもずっと頭に引っかかる。ラジオでしか聴いたことがないけれども、千明ちゃんにそっくりな声だった。不思議な男の子だった。
あたしのファンだと言っていた。仕事をしなくなって一年以上たつのに何故いまさら…。しかも、同年代の男の子から。今のあたしに声がでないことを知ったら、あの子も幻滅するだろうなと思う。
そうだ、このことを千明ちゃんのラジオに送ろう。そう思ってハガキを手に、今日あった内容を書いて送った。末尾には『また手紙書きます。』と書いた。そう書くことで、千明ちゃんと繋がってるように感じられた。
それからまたしばらくたったある日。クリニックが嫌で部屋に引きこもっている時に、なぜか千明ちゃんが家に来た。
「はじめましてっ!万丈千明です♪」
ドア越しに聞こえてくるその声は、まさしく千明ちゃんの声だった。ママから声がでないことを聞いたらしい。
ショックだった。千明ちゃんには知られたくなかった。ずっと、そのことを隠してハガキを書いてきたのに。
「よかったらおしえてくれない? どうして声が出なくなったのか…。」
ラジオのように、親身になって千明ちゃんは聞いてきた。でも、あたしは悩み相談をしていない。声が出なくてもそれでいい。声がでないあたしのことは、放っといてほしい。
そう思って思わず、『帰って。』そう書いて、ドアの下から千明ちゃんに渡す。動揺していて普段送っている手紙と比べると汚くなったけど、仕方がない。
これで、帰ってくれるのではないかと思った。だけど、千明ちゃんの次の言葉にあたしは驚かされた。
「私、零那ちゃんにあこがれて声優になったんだ…!!」
先ほどまでと違って、切実な声だった。
「だからまた…、もう一度、零那ちゃんの声が聞きたい…。…私、まってるから。」
そう言った後、足音で離れていくのが分かった。
ベランダにでて、千明ちゃんが出ていく様子をうかがう。後ろ姿しか見えなかったけれども、黄色いロングの髪の毛の女の子と、男の子が一人。
彼氏かもしれない。千明ちゃんみたいに声がかわいくて優しい子なら、いてもおかしくない。あたしには関係のない世界だ。
それから1か月がたち、千明ちゃんの写真集が発売されたというので買いに行った。
確かに、あの時チラッと見えた女の子だ。声だけじゃなく、顔もかわいい。あたしが想像している顔とほとんど同じだった。不思議だった。なぜこうも、想像通りなのだろうと。
あれ以来、あたしはラジオに手紙を送っていないし、千明ちゃんが訪ねてくることもない。
きっと、そのまま忘れてしまっているのだろうと思う。あたしがきっかけで声優になったという言葉はうれしかったけど、声がでないと知ったなら幻滅していることだろう。
今思えば、ラジオにハガキを送ったのが間違いだったと思う。あんな、学校生活を楽しんだり悩んだりしている子が聴くようなラジオに、不登校のあたしは場違いだった。
だからもう、あたしのことなんて気にもしていない。でも、ちょっとだけ後悔もしている。あの時、ドアを開けていたら、千明ちゃんと友だちになれたかもしれない。一瞬そうが考えたけど、やっぱりそんなことはないのだろうなと思う。声の出ないあたしに友だちなんてできるはずないんだから。
そう思っていると時に、インターホンが鳴った。玄関から千明ちゃんの声が聞こえる。
一瞬迷った後、部屋を出て階段を降りた。確かにそこには写真集に載っていた千明ちゃんがいた。
「零那ちゃん!」
千明ちゃんはそう叫んだあと、ミュージカルのオーディションのお知らせを手に掲げた。
「零那ちゃんもいっしょにオーディション受けよっ!」
予想外の言葉だった。声がでなければミュージカルなんてできない。
「私にハガキ書いて送ってきたってことは、私に気づいてほしかったんだよね?」
千明ちゃんの言葉にビックリする。いや、そんなことはない。一瞬そう思ったけど、心の中で湧き上がる感情が違っていた。
千明ちゃんのその言葉で、あたし自身、気づいていなかった自分の気持ちに気が付いた。ハガキをだしたのは、ハガキ代がもったいないからじゃない。誰かに気づいてほしかったからだと。部屋に閉じこもって誰にも気づかれないあたしに、気づいてほしかった。
本当は、心のどこかで恋愛したり友だちと遊んだり、他のラジオリスナーと同じようなことをしたかった。声が出なくていいなんて、ただ逃げているだけだ。それを、千明ちゃんは気づかせてくれた。
「千明ちゃん!」
あたしは心の中で叫んで千明ちゃんの胸に飛び込んだ。声がでるなら、千明ちゃんの耳にも届いたことだろう。
「ぁ…り…が…と…」
久しぶりに声をだそうと思ってもうまく声がでない。千明ちゃんにも聞こえてるか分からない。でも、伝えたかった。こんなにも一生懸命になってあたしのことを考えてくれてありがとうって。自分の声で伝えたかった。
こんな状態でオーディションなんて受かるのだろうかと不安に思った。
でも、千明ちゃんと一緒に仕事をしたい。ミュージカルにまたでたい。その気持ちは、それまで部屋に閉じこもっていた分の気持ちが一気にあふれでたのではないかと思うぐらい、強かった。
それからのあたしは必死に練習をしてオーディションに合格し、一生懸命リハビリや稽古にはげんで、ミュージカルがはじまる夏には問題なく声がでるようになっていた。
一時期は辛くてめげそうになることもあったけど、その度に千明ちゃんが励ましてくれ、その度に頑張ろうと思えることができた。
声がだせるようになったことで、千明ちゃんともお喋りすることができ、それがとっても楽しかった。こうやって声がでるようになると、何で今まで声が出ないほうがいいと思えたのか不思議になる。こんなに楽しくお喋りすることは楽しいというのに。
時々、千明ちゃんと、前に一緒に家に来た京極くんが話しているのが遠目で見ることがあった。どうやら、彼氏じゃなくて友だちだという。漫画を読んでいると、男女の友だちでも、どちらかは好きなイメージがあったけど、この二人は確かに友だち同士のように思えた。
京極くんと話している時の千明ちゃんは少し、男の子っぽい口調になる。それが、普段の千明ちゃんを垣間見れているようでうれしかった。
そして、あっという間にミュージカルは千秋楽になった。
本来、ダブルキャストなので別々の日程での出演となるけど、千秋楽ということもあって最後の挨拶に出演させてもらえることになった。
今まで千明ちゃんとは、稽古では一緒にやっていたものの、一緒に舞台にたつことはほとんどなかったのでうれしかった。
だから、今度は一緒に舞台にあがる仕事がしたいなと思う。今回は千明ちゃんがミュージカルのオーディションを見つけて誘ってくれたけど、あたしも探してみようかなと思う。一緒に舞台にでれそうなオーディションがあれば、今度はあたしのほうから誘いたいと思った。
その気持ちを伝えたいと公演終了後、千明ちゃんを見かけると、「これからも、ずっと、ず~っと、いっしょにがんばろーねっ!」と伝えた。
ただ、千明ちゃんは疲れているのか、その日はずっと元気が無いようだった。少し、声の調子も悪そうだった。
「いいな、千明ちゃんは。声がかわいくて。」
駅の改札まで見送りに行くとき、何気なくそう話した。もう会えないということはないだろうけど、しばらく会えなくなるこのタイミングで、あたしが声を出さないようになった理由を伝えることにした。前に千明ちゃんから聞かれたものの、ずっと伝えてないままだったから。
「あたしね、自分の声、キライなの。」
それは、ママにも言ったことがない自分の思いだった。今まで誰にも言ったことがないのに、千明ちゃんになら何の抵抗もなく言うことができた。
それを受けて、千明ちゃんが言う。
「あたしも、自分の声、あんまり好きじゃなかった。」
千明ちゃんにも声がコンプレックスだといって驚いた。ただ、ある日をさかいにコンプレックスを武器と考えて利用してきたという。ただ、その時の千明ちゃんはどこか物憂げな表情だった。
そうして千明ちゃんは大人になりたくないと思っても否応なしに大人になっていくということを語った後、「だから、そんな自分も受け入れていかなきゃだめなんだよね」と意味深な様子で千明ちゃんはつぶやいた後、「オレ、零那の声、好きだよ! だから、自信もってね!」と言って千明ちゃんは改札に入っていった。
ちょっとよく分からなかったこともあるけど、千明ちゃんは励ましてくれたのだと思う。昔のように高い声がでなくなったとしても、今の声には今のよさがあると。
「よしっ!」
あたしは気合をいれなおし、千明ちゃんが褒めてくれたこの今の声で、仕事を頑張って続けようと決意した。
いつかまた、千明ちゃんと共演できる日を信じて……。
何かがおかしいと気づくまでに、それほど時間はかからなかった。
千明ちゃんとやりとりしていたメールアドレスがアドレス不明で返ってくるようになった。
千明ちゃんの所属する事務所の村崎さんに尋ねてみると、学業優先で辞めたという。住所も電話番号も分かっていない。完全に連絡方法が途絶えてしまった。
頭の中がパニックになった。辞めるなら辞めるでどうして話してくれなかったのか。また、一緒に仕事ができると思ったのにもう会えないのかと…。ショックだった。
ただ、あたしはあきらめきれなかった。千明ちゃんがあたしを見つけてくれたように、今度はあたしが千明ちゃんを見つけるんだと決意した。
まずは、パソコンでネット検索してみることにした。「万丈千明」と入力して検索する。事務所のサイトやWikipediaと並んで、『万丈千明ちゃんの通ってる小学校は?彼氏はいる?調べてみました!』というブログ記事がヒットした。
一度、唾を飲み込み、そのページを開く。スクロール量の長いページだと分かった。思ったより簡単に見つかりそうだと思った。ゆっくりとスクロールして文字を読んでいく。千明ちゃんが過去に受けたインタビューのことが書かれている。「普段は友だちと、『今日の給食は何かな?』と話しているようです」と書かれている。あたしも千明ちゃんと学校生活したいなと思ったけど、今はどうでもいい。どこの小学校なんだと先を読んでいるとスクロールが止まった。末尾には、「調べてみましたが、分かりませんでした!」とあり、ガッカリする。なぜ、調べてわからなかったことを記事にするのか……。
やっぱりそう簡単には見つからないかと思ってパソコンを閉じようとし、ふと京極くんと仲がいいのを思い出した。
検索欄に「京極瞬」と入れて検索する。またもや、『京極瞬くんの通ってる小学校は?彼女はいる?調べてみました!』というブログ記事がヒットした。
あまり期待しないでリンクをクリックして読み進める。またまたスクロール量が多い。「遠足では仲のいい友だちと別の班になってしまったそうです」と、またもやどうでもいいことが書いてある。やっぱり、これも見つからないかと思っていると、ふと気になる記述が目に入った。
「どうやら区立の小学校の演劇クラブに似たような子がいるようです。演劇クラブのホームページの写真に京極くんらしき子が写っていますね」
先ほどの千明ちゃんの記事と違って、断定的ではないけど、どこの小学校に通ってるかが書いてあった。どうやら、誰かが掲示板に「これ、京極瞬じゃね?」と掲示板に書いたようで、一緒に演劇クラブのURLが書かれてあった。
そのURLをクリックして演劇クラブのページを見てみる。確かに京極くんらしき子が写ってる写真があった。
そのホームページには過去の活動履歴も載ってあり、遡っていく。1年半ほど前に区民会館で行われた劇の写真に見覚えのある顔があった。
昔、あたしの家の前にいた男の子だ。不思議と一度しか見ていないのに、鮮明に思い出せた。確かあれは、1年半ほど前。つまり、この劇が行われた日と同じぐらいの時期だったはずだ。
一つ前の記事では白雪姫の劇が紹介されていた。その写真に載っている白雪姫役の子は、髪色は違うが千明ちゃんに似ている。ただ、先ほどの男の子のようにも見えて…。
そこであたしは気づいた。今まで全く考えなかったけれど、そう考えると納得できる。
千明ちゃんはあの時の男の子だったのだと。
最後のあの、意味深な発言も、京極くんと話すときの男の子っぽい口調も理解できた。そして、辞めたのも男の子だからなのだろうと思った。声の調子が悪そうだったし、声変わりが近い可能性だってある。実際、最後に会った時に、大人になりたくないと思っても否応なしに大人になっていくというのを語っていた。あれは、声が変わっていくということを言いたかったのかもしれない。
それが辞めた理由だったら、確かにあたしに言えないかもしれないと思った。あたしをずっとダマしていたことになる。でも、不思議と嫌な気持ちにならなかった。むしろ、そこまでしてあたしのために一緒にいてくれたのかと考えるとうれしかった。
千明ちゃんの顔を初めて見た時に想像していた顔とほとんど同じだったのも、あの時の男の子の印象が強かったからだろうと思う。
でも、それだけでは説明できないこともある。一度だけしかみていない男の子の顔を覚えていることだ。でも、それも今気づいた。あたしは千明ちゃんの声に惚れていた。そして、その声をもった男の子が表れて、強く印象に残った。いまだに顔を覚えているぐらいに。
これは多分、恋なのだと思う。今までろくに異性の子と接してこなかった初めての恋。初恋だ。
それが分かった後のあたしの行動は、自分でも驚くぐらい積極的だった。
まず、その小学校の近くの中学校を調べて、その校区を調べた。そして、その校区内に一人暮らしをすることに決めた。もともと、不登校のあたしは、中学校は、あたしの小学生時代のことを誰も知らない遠くの学校に通おうと思っていた。それなら、千明ちゃんと一緒の学校がいいに決まってる。
もちろん、未成年が一人暮らしをするには両親を保証人として家を借りることになるので、両親を説得することになる。
どうすれば説得できるか。これまでにないほど真剣に考えた。そうして思いついたのが、東京からだと通勤が楽になるということ。ただし、それだけだと弱い。今住んでいるところだってじゅうぶん通える距離だ。なので、ずっと不登校だったけど中学からは通うようにしたい。ただ、今の家の校区の中学校だと、不登校だったことを知っている子と一緒になるので、中学は全く違う場所に通いたいということを告げようと思った。もちろん、家賃や光熱費は自分の仕事で得たお金からだすということも伝える。
説得は予想通り難航した。何度も頭を下げてお願いしたが受け入れてもらえない。ここからも通えるし、不登校でも勉強はしてたのだから、偏差値が低くていいから私立中学校に受験すればいい。そればかりだ。
さすがに30分もすると、見かねたママが、「他に理由があるんでしょ?」と尋ねてきた。さすがママだ。
どうしようか迷った末、正直に「千明ちゃんと一緒の学校に通いたい」と答えた。いろいろ理由を考えた中で、正直な理由を言わなかったのは、これはあたしのワガママだからだ。多分、この理由じゃ受けいれられない。そう思っていた。
だけど、あたしの予想に反して、それを聞いたママは一度ため息を吐き、「仕方ないわね」と答えた。
「あの子は、零那にとって恩人だものね」
そうだ。確かに、あたしにとって千明ちゃんは恩人なのだ。ずっと部屋に閉じこもっていたあたしを、外の世界に連れ出してくれた恩人。きっと、ママにとっても千明ちゃんの存在はうれしかったのだと思う。
「ありがとう。ママ」
そして、入学式の日になった。数日前に引っ越しもし、制服も用意した。制服に身にまとって鏡をチェックする。久々の学校だ。うまくやれるだろうかと少し緊張する。
少し早めに家を出て校門前に立った。門に入っていく男の子を見ていくが、なかなかあの子はあらわれない。
そもそも、行き当たりばったりすぎたかもしれないと今更ながら後悔する。小学校が分かったからと言って、その近くの中学校以外に通うことになる可能性だってあるのだ。今になって、もう少し調べておけばよかったと後悔する。あたしは心の中で願った。どうか、あの子もこの学校でありますようにと。
そう思っていると、彼がやってきた。一目見てすぐに分かった。あの時の男の子だ。隣には京極くんもいる。
「千明…ちゃん!」
思わず呼び掛けた。彼は千明と呼ばれて不思議そうな顔をしていたけど、あたしには分かる。胸のときめきが全然違う。
「…やっと…、見つけた…!」
「黙っていなくなって、ごめん!」
彼はそう言って頭を下げた。
「千明は、このまま何も言わずにいなくなったほうがいいんだろうと思って…。今まで零那をダマして一緒にいたわけだから…」
「いいの。千明ちゃんがあたしを見つけて助けてくれたことには変わりないし、そこに男とか女とか関係ないと思う」
あたしがそう言うと、彼はくすぐったそうに笑って照れたような顔をした。
「あっ! そうそう。オレの名前なんだけど、本名は十河太一って言うんだ」
「太一くんだね。今日からまたよろしくね」
あたしがそう言うと、太一くんは照れたような顔になり、「こちらこそ」と答えた。
残念ながら、太一くんとは別のクラスになってしまった。さすがに、中学校は同じになれても、そこまで都合よくはいかなかった。ただ、クラスの女の子には声をかけてくれる子もいて、案外すぐに仲良くなれた。中には、ミュージカル好きで『千載一遇物語』を見て知ってくれた子もいて、話が盛り上がった。
まさに、千明ちゃんのラジオを聴いてあたしが望んでいた学校生活だった。友だちと笑ったり、時にはケンカもしたりするのかもしれないけど、それもきっといい思い出になるのだろうと思う。
もちろん、太一くんとも一緒に話すことも多かった。廊下ですれ違った時には話をするし、昼休みになると一緒にご飯を食べることもあった。
あたしがお弁当を作ってきて二人で食べたり、食堂でご飯をごちそうになることもあった。正直、おごられるのは少し戸惑ったのだけど、「千明」の時に稼いだお金が結構あるという。「零那に会うために千明になったのだから、千明で稼いだ分は零那にも使わせてほしい」と言われた時は少し気恥ずかしかったけど、嬉しかった。
時には休みの日に一緒にミュージカルに観に行くこともあった。ミュージカルを見た後はファストフードで食事をしながら感想。あの場面のあそこがよかったとお互いに感想を言い合う。
多分、周りから見たらデートに見えただろうし、あたし自身、デートだと思っている。多分、太一くんもそうだと思う。
でも、よくよく考えると、お互い気恥ずかしいのか、「好き」とは言ったことがない。まあでも、こういう恋愛もありかなと思う。お互い、心が通じ合えているから、わざわざ「好き」何て言わなくてもいいのだろうなと。
千明ちゃんがいなければ今でも声がでないままだったかもしれない。そう考えると、本当に声が戻ってよかったと思う。
「声なんて出なくていい」と思ったあたしに言ってやりたい。声が出た後には、いっぱい楽しいことが待っているからって。
入学して2か月が過ぎた6月始め。仕事が久々に休みということもあって、あたしは太一くんと京極くんが所属している演劇部を見学させてもらうことにした。演劇部にはあたしも入ろうか迷ったけれども、最近は仕事が忙しくなってきたので断念していたのだった。
演劇部といっても、やっていることは基礎練習だ。発声練習として「アメンボの歌」を暗唱したり、筋トレに腕立て伏せや腹筋をしたりしていた。
ちょうど、筋トレが終わって休憩している時にあたしは声をかけた。
「太一くん!」
突然、見学に来たからか、太一くんは驚いた顔を見せた。といっても、その驚いた顔が見たかったのだけど。
「こういう基礎練習は養成所にいる時によくやったよ。小学校の演劇クラブは遊びの延長みたいなもんだったなって思う。中学の演劇部はかなり本格的」
太一くんは笑顔を見せながらそう言った。
「基礎練習は大事だよね。あたしも家でやってるよ。発声練習は、今の家だと近所迷惑になるから枕に口を押さえつけてやったりして」
「あるある。後、布団をかぶってやったりね。夏には暑くてやりたくないけど」
こうやって、演技の練習の話をすると千明ちゃんと稽古を受けていた時を思い出す。あの頃みたいに、また一緒に劇の練習ができたらいいなと思う。やっぱり、あたしも演劇部に入ろうか。いやでも、仕事がちょくちょく入るとやっぱり迷惑になるかな。
太一くんはまた仕事として演劇をやるつもりがないのだろうか。そしたら、また一緒に舞台にたてるかもしれないのになと思った。
そんなこと考えていると、ふと近くに下を見てキョロキョロしている女の子が目に入った。クラスは違うけど、たまに廊下で見かける、軽く髪をカールにした女の子。その顔には、どこかで見覚えがあった。
「百花、ヘアゴムあったよ!」その女の子の友だちと思われる子が、女の子にヘアゴムを渡した。どうやらヘアゴムを落として探していたらしい。
百花という名前を聞いてあたしは思い出した。昔、あたしがまだ高い声をだせていた時に参加したミュージカル『点と線との阿弥陀くじ』でダブルキャストで同じ役を演じた、阿僧百花ちゃん。
太一くんが水を飲んでいる時に女の子に話しかけることにした。
「もしかして、阿僧百花ちゃん?」
女の子は一瞬、驚いた顔になったと思ったら、すぐに笑みをうかべた。
「うれしい! 覚えててくれたんだ。毛利零那ちゃんだよね?」
どうやら、当たっていたらしい。「そうそう、昔ミュージカルの点と線の…」そこまで言ってる時に、急に後ろで「あーー!!」という大きな声が聞こえた。男の子の声だ。
振り向くと、その声は京極くんだということが分かった。
「太一、こっちに来い。ちょっと話があるから」
「えっ? な、ちょっと何でだよ…」
「いいから早く」
そういって京極くんは太一くんを連れて、離れていった。その行動にちょっと不可解さを覚えたものの、あたしは百花ちゃんに体の向きを戻して、話し始めることにした。
『点と線との阿弥陀くじ』が千秋楽になった後、百花ちゃんは演劇の仕事を辞めた。正確には、辞めたというよりは続けなかったというのが正しい。劇にでたのは、『点と線との阿弥陀くじ』だけだったから。もともと、ミュージカルは好きでよくみていたそうなのだけれども、そんなある日に、演劇関係者にスカウトされたらしかった。次にやる劇の『点と線との阿弥陀くじ』のモコ役のイメージにあっているということだ。
ただし、百花ちゃんには演劇の経験が無かったので、同年代のあたしもダブルキャストで選ばれたうえで一緒に稽古をすることになった。
百花ちゃんの演技は、確かに最初こそつたなかったものの、稽古を重ねていくうちにみるみるうちにうまくなっていった。あたしとしては、今まで同じ役の稽古を練習する仕事友だちはいなかったので、そういう友だちができたと思えてうれしかった。だから、演技の仕事を続けなかったと知った時は残念だった。
「演劇は辞めたって聞いたけど、ずっと続けてるの?」
あたしのその質問に、百花ちゃんは少し申し訳なさそうな顔をして答えた。
「ううん。小学生の時は演劇クラブには入ってなかったんだけど、十河くんや京極くんの演技を見ていたら、あたしもまたやりたくなって…。」
「そうなんだ。あたしもしばらく演技の仕事をやれない時があったんだけど太一くんの声を聴いてまたやりたくなって……」
と、そこまで言って「しまった」と思った。太一くんと言ったものの、千明ちゃんのイメージで話してしまった。
そんなあたしの動揺に気づいたのか、百花ちゃんは小さく小声でつぶやいた。
「万丈千明ちゃんだよね」
知っていたのかと驚いた。
「あたしも最近知ったばかりなんだけどね。『千載一遇物語』の千秋楽の時だったかな…。あっ、でも、このことは多分、あたしと京極くんしか知らないから、秘密でね」
百花ちゃんの言葉を聞いて、知っていたのかとちょっとだけ残念な気持ちになった。千明ちゃんが太一くんだと知っているのは、京極くんとあたしだけだと思っていたから。あたしが知らないだけで、太一くんと百花ちゃんは案外、親密な仲なのかもしれない。
その後、百花ちゃんは少し迷った素振りを見せた後、口を開いた。
「…たまに、十河くんと零那ちゃんが一緒に話してるところ見かけるんだけど、二人はとってもお似合いだと思う。これからも、応援してるね。」
ちょっとだけ衝突な発言に思えた。あたしと太一くんについての応援の言葉だったけど、その時の表情はどこか悲し気だった。
理由はよく分からなかったけど、あたしは素直に「ありがとう」と伝えた。
しばらくして、テスト期間となった。テストが近づくと部活動は休みとなるようで、演劇部も休み。あたしは初めて太一くんと二人で帰ることになった。太一くんが玄関で待っていてくれたのだ。
男女二人並んで歩いて帰る。これも前からやってみたかったことだ。また一つ、夢がかなった。
「そういえば、『ペンタゴン娘』の最終回見たよ。すごいよかった。ちょっと下ネタが多くて恥ずかしかったけど…」
今年から精力的に仕事を再開したあたしは、千明ちゃんがやっていた声優という仕事に興味をもって、アニメ声優のオーディションも受けていった。
『ペンタゴン娘』はあたしの声優デビュー作のアニメだ。主人公の妹役で、それなりに出番のある役でうれしかったものの、数学好きの女の子たちが下ネタを繰り広げるというコメディアニメだったということもあって、ちょっと演じるあたし自身も気恥ずかしかった。
ただ、今までやったことがない役だったということもあり、いい経験にはなったと思う。「パンティーの理想的な比率は黄金比、つまり1:1.618です!」なんてセリフは今後、言うこともないだろう。
「あたしもちょっと恥ずかしかったけど、やってよかったと思う。でも、アニメ声優の演技って難しいね。立ち位置が決まっているわけではないから、どのマイク使えばいいんだろうって最初分からなかった」
「そうだよね。オレも最初よく分からなくて、一番奥が比較的空いてるなって思って使ったら、そこはベテランの方が使うものって怒られたよ。だから、次は入口近くのマイクを使うようにしたんだけど、また勝手にマイク変わっちゃダメって怒られて。難しいなって思ったよ。でも、そうしたらベテランの声優さんが私のほうのマイク使っていいから、周りを気にしないで演技に集中したらいいって言ってくれたんだ。普段通りのあなたの演技をやったらいいって。その言葉をきいてもっと堂々とやろうと思って、役になりきることができたと思う」
太一くんは懐かしそうに、楽しかった昔話を語った。
「周りを気にせず演じるのがいいのって分かるけど、難しいよね。あたしも、昔は周りなんか気にせずにのびのびと演じられたんだけど、高い声がでにくくなってからは周りの目を気にするようになった。それが余計に苦痛になったのかなって今は思う。今は、太一くんが好きといってくれたこの声が自分の武器だと思って、自分らしい演技をやってるつもり。」
「それがいいよ。オレにとっては、昔の零那も今の零那も、自分らしい演技ができていてとてもいいと思う」
太一くんがそう言って、ふと思った。そういえば、太一くんは何を見てあたしを知ってくれたのだろうと。
「そういえば太一くん、前にあたしに憧れて千明ちゃんとして声優になったって言ってくれたよね? 何の芝居だったの?」
太一くんの隣を歩きながらあたしはそう言った。太一くんは何か思い出したように続ける。
「ああ。そういえば言ってなかったっけ。『点と線との阿弥陀くじ』だよ。あのミュージカルは本当良かった。あれで零那を見てオレは憧れたんだ。今思うと、初恋だったのかなって思う。って、改めて言うと、ちょっと照れ臭いけど……」
太一くんはそう言うと少し顔を赤らめた。あたしが太一くんを初恋なように、太一くんもあたしのことを初恋だという。そう考えると、ちょっと照れ臭い。多分、あたしも顔は赤いと思う。どうやって話を続けようかと迷って、百花ちゃんとの話を思い出した。
「そういえば、聞いてるかもしれないけど、あのミュージカルってあたしと百花ちゃんとのダブルキャストだったんだ。ダブルキャストって初めてだから、一緒の役の稽古をやるのは新鮮で楽しかったなぁ。この学校になってまた百花ちゃんに会えてビックリしちゃ……」
そこまで言って気づいた。いつの間にか隣に太一くんがいない。後ろを振り向くと、太一くんは茫然と立ち尽くしているようだった。
「どうしたの?」
あたしの問いかけに気づいた太一くんは、あたしの顔を見て、わざとらしく笑顔をむけて歩き出した。
「いや、なんでもない。そっか。そうだよね。あのミュージカルは本当よかったよ…」
とてもわざとらしい言い方だった。ミュージカルが良かったというのはさっき言ったのにまた繰り返す。まるで、あたしが百花ちゃんの話をしなかったような感じだ。
それからの太一くんはどこかぎこちなかった。こちらから話しかけてもわざとらしい笑顔で答えるだけだし、何より太一くんのほうから話しかけてくれることがほとんど無くなった。
何か悪いことをしただろうかと考えても思い当たる節がない。ただし、間違いなくいえるのは、『点と線との阿弥陀くじ』であたしと百花ちゃんがダブルキャストだったと話した時から様子がおかしい。
仕事中でも考え事をしてしまい、注意されてしまった。ダメだ。今は仕事に集中しなきゃ。
今日の仕事は『スパイスキッズ2』の吹替だ。もともとは千明ちゃんが吹替をしていた役だけど、千明ちゃんが引退してしまったので再オーディションが行われた。そこで運よく、あたしが選ばれたのだった。声質は少し違うが、元の役者さんも成長していることを考えると、むしろあっているのではないかという意見があったという。
ただし、他の配役は変わらず。なので、今日は京極くんと一緒の仕事となる。
「お疲れ!」
休憩中、京極くんが缶のカフェオレを渡してそう言った。
「ありがとう。京極くんの、吹替の演技すごい上手だなって思った。あたしは実写吹替は初めてだから、口の動きにあわせるのかちょっと難しいなって思っちゃった」
「あぁ。そのへんは、あいつに…、万丈千明にいろいろアドバイスしてもらって良くなったと思う。」
なるほど。さすが千明ちゃんだ。多分、親身になってアドバイスしたのだろうと思う。それこそ、苦戦しているのを感づいて自分から言ったのかもしれない。
「でも、今日の毛利はそれだけじゃなくて普段と違うように思ったけど、何かあったのか?」
京極くんのその質問にどう答えようか迷った。何でもないということもできるけど、心のモヤモヤが気になるので正直に話すことにした。
「…ちょっとね。最近、太一くんの様子がおかしいような気がして…」
「太一が? 何かあったのか?」
「何かあったわけじゃないんだけど、実は…」
あたしは、百花ちゃんと昔、ミュージカルのダブルキャストで同じ役を演じたことがあるということ、それを太一くんに伝えたこと、それ時から太一くんの様子が変な気がするということを話した。
「あぁ、そういうことか……」
京極くんはどこか納得したような、それでいてどこか残念そうな声でそう言った。ふと、あたしと百花ちゃんが話していると不自然な行動で太一くんとどこかに行ったのを思い出した。何か知っているのかもしれない。
「何か知ってるの? だったら、教えてほしい」
「いや、その…」と京極くんは言って少し迷った素振りを見せた後、「ここでは何だから、仕事終わりに時間とれるか?」と言った。
仕事終わり、京極くんとカフェに入り、対面で席に座った。なかなか京極くんは口を開かないので一度、頼んだ紅茶を飲む。いれたばかりの紅茶は熱かった。
「初めて万丈千明と仕事をした時に記者会見があったんだけど、そこであいつ、昔ミュージカルで見た女の子に憧れて声優になったって言ってたんだよ」
初めて千明ちゃんが家に来た日のことを思い出す。「私、零那ちゃんにあこがれて声優になったんだ…!!」。あの時、千明ちゃんはそう言っていた。
「ただ、よくよく話聞いてみると、ミュージカルのタイトルも、憧れた女の子の名前も覚えてないっていうから、ネットがつながるパソコン借りて調べたんだよ。観に行った年や場所を聞いて絞っていって、そしたら『点と線との阿弥陀くじ』というタイトルだとわかって、キャスト一覧が載ってるサイトを見つけて調べたんだよ。そこで毛利の名前を見つけた……」
京極くんは一度話を止めると、一度紅茶を口にして、再度口を開けた。
「その後、万丈千明が毛利に会いたがっているから少し調べたんだよ。ネットのBBSで仕事をやめたとかいう噂が書かれていたのはみつけたけど、写真はなかなか見つからなかった。そこで試しに、『点と線との阿弥陀くじ』と役名の『モコ』で検索をかけたらヒットした。阿僧によく似た女の子の写真だった。」
「それはだって、同じ役だったか…ら…」
そこで気づいた。京極くんが言おうとしていることが。
「オレは、阿僧に似ているから気になっているのかと思って万丈が太一だと思った。実際にはちょっと違ったようだけど、太一もミュージカルで見た女の子と阿僧はよく似ていると思っていたらしいし、阿僧じゃないかと最初は思っていたらしい」
「つまり、太一くんが見たっていうのは…」
「毛利じゃなくて阿僧だった可能性がある」
一瞬、ザワついていたカフェの中が、あたしの周りだけ静寂に包まれたような気がした。
「多分、あいつも役名の『モコ』だけは覚えてたんだと思う。それで、キャスト一覧見て毛利だって…。オレも、初めて阿僧からダブルキャストだと聞いた時は驚いた。急いで前にみたキャスト一覧ページを見返したら、別日程のページがあって、そこに『阿僧百花』と書かれてあった」
心臓の鼓動が早くなる。心を落ち着かせるためにあたしは紅茶を一口飲んだ。先ほどまで熱かった紅茶はだいぶ冷めていた。
「ごめん。オレのせいだ。オレがもっと調べていればこんなことには…」
「ううん。京極くんは悪くないよ。というより、この問題は誰も悪くない。むしろ、千明ちゃんと出会わせてくれてありがとう」
そう。きっと、その時にあたしの名前に気づいてくれなかったら、ラジオであたしのハガキを読まれることもなかったと思う。そうしたら、もうハガキもださなかったし、そもそもあたしの家に訪ねてくることもなかった。感謝してもしきれないぐらいだ。
『今思うと、初恋だったのかなって思う』
先日の太一くんの言葉を思い出す。初恋の相手はあたしじゃなくて百花ちゃんだったんだと。あたしの発言で、太一くんもそのことに気づいたのだろう。
そう考えると、急に胸の中が急にそわそわして涙がでそうになったけど、なんとかこらえる。でも、胸の中のそわそわは消えることが無かった。
京極くんは、その後も何か話しているようだったけど、あたしの耳には入ってこなかった。
数日後、廊下を歩いていると、教室内で太一くんと百花ちゃんが話しているのを見かけた。
最近あたしと話すときに見せるぎこちない笑顔と違って、太一くんは楽しそうに笑っている。百花ちゃんもどこかうれしそうだ。
ふと先日、百花ちゃんがちょっと悲し気にあたしと太一くんを応援してくれたことを思い出す。
今思い返すと、百花ちゃんも太一くんのことが好きなのではないかと思った。百花ちゃんは、太一くんがあたしのことを好きだと思ってるから、無理に応援しようとしているのではないかと。
翌日の昼休み、あたしは百花ちゃんを、屋上に呼んだ。誰もいないところで二人で話したいことがあった。
外は雨は降ってないが、曇り空だ。梅雨時だから仕方がない。
「どうしたの? 話って?」
「うん。ちょっと気になってることがあって…」
ここにきて心臓の鼓動が早くなった。一度深呼吸する。
「百花ちゃんって太一くんのこと好きなのかなって…」
「えっ!?」
百花ちゃんはあたしの言葉に驚いた様子だった。それはそうだろうと思う。自分ももう少しうまい言い方はなかったのかと思うけど、思いつかなかった。
「す…、好きか嫌いかというと好きだよ。で、でも変な意味じゃないから。そ、その、前にね、実は…、こういうこというのもなんだけど、十河くんに告白したことがあるの。でも、その時に言われたんだ。零那ちゃんのことが気になってるって。だから、好きな人に気になっている人がいるならその恋を応援しようと思った。これは本心だよ」
百花ちゃんは少し動揺しながらも、真っすぐな目でそう答えた。予想通り百花ちゃんは太一くんのことが好きだった。告白までしたという。きっと、昔見たミュージカルの女の子が百花ちゃんだと気づいていたら、その告白を受けただろうと思う。でも、それなら話は早かった。
「勘違いしているみたいだからいうね。あたしと太一くんは恋人なんかじゃない。告白したりされたりしたこともなければ、好きだと言ったこともない。それにね、太一くんがあたしを気になってるっていうのは勘違いだったみたいなんだ……」
「えぇっ!? そ、そんなことないよ。だって、太一くんは零那ちゃんの声が戻ってほしいと必死に考えて…」
「違うの!!」
思わず、百花ちゃんの声をさえぎって、大きな声をだしてしまう。
「太一くんの初恋は昔見たミュージカルの『点と線との阿弥陀くじ』でみた女の子なんだって。タイトルと役名を調べて、あたしだと思ったみたい。でも、違った。本当は百花ちゃんだったんだよ」
「で、でもそれだけあと零那ちゃんだって……」
「…あたしの名前を見るまで、百花ちゃんじゃないかって思ってたんだって。そりゃそうだよ。だって太一くんがみたのは百花ちゃんなんだから。太一くんも最近、そのことに気づいたみたい」
思わず語気が強くなってしまった。ちょっとだけ、なぜあたしがでてた回じゃなかったんだと思って辛くなったが、どうしようもない。
「……」
百花ちゃんは何も言いかえしてこなかった。多分、頭の整理ができていないのだと思う。
「さっき百花ちゃん、『好きな人に気になっている人がいるならその恋を応援しよう』って言ってたよね。あたしも同じ気持ちだよ。」
あたしはそれだけ言うと「じゃあね」と言って、百花ちゃんを置いて屋上を後にして急いで階段を駆け下りた。言い逃げというのはこういうことだと思う。言いたいことだけ言って、あたしは逃げた。今は百花ちゃんの顔をまともに見れる気がしなかった。
次の日、ホームルームが終わって帰ろうとしていると、百花ちゃんと太一くんが二人、屋上のほうへ向かって行くのが目に入った。一瞬、百花ちゃんと目が合う。何かを決意したような顔だった。
あたしは階段で下に降り、下駄箱で靴を履き替えて一人、校門をでた。
多分、今頃、百花ちゃんは太一くんに告白していることだろう。太一くんは百花ちゃんのことを初恋の人だと気づいたのだから、そのまま付き合うことになる。
もともと、あたしと太一くんは恋人として付き合っているわけではなかった。ただ、もともと一緒に仕事をしたことがある間柄ということもあってよく話していただけだ。
彼女ができた太一くんはあたしと話すこともしなくなる。でも、そんなの問題ない。クラスも違うし、部活も違う。でも、太一くんが幸せならそれがあたしの幸せだ。
だから、これでよかったんだと思う。
そう思った時、頬に涙が伝っていくのを感じた。すぐに、腕で涙をぬぐう。
「おかしいな…。何で泣いてるんだろう…。」
あたしは役者なんだから、感情にとらわれて泣くなんて許されない。だいたい、泣く必要なんかどこにもないはずなのだ。何も悲しいことなんてないのだから。
そう思っても、一度溢れてきた涙が止まることはなかった。
いつの間にか雨が降ってきたけど、あたしはそれに気づくこともなく歩いていた。
→後編