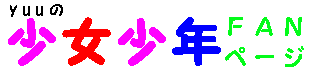望月マユカ編~最悪のバレンタイン~
「今日、帰りにチョコ買いに行こ!」というクラスメイトの女子のお喋りで、望月マユカは今日が2月13日だということを思い出した。明日はバレンタインデーだ。 どおりで最近、男子達がそわそわしているとマユカは思った。バレんタインで女子からチョコをもらえるのを期待しているのだろうと。 ただ、そんな一年に一度のイベントも、マユカにとってはくだらないとしか思えなかった。バレンタインデーにチョコレートを渡す風習なんて、日本のお菓子会社の策略だ。キリスト教圏でチョコを送る風習なんてない。 そうして、ホワイトデーにはまたお返しをしようと策略する。自分はそんなものに乗せられる人ではないと、マユカは思った。 「バレンタインかぁ…」 マユカの隣の席に座っている星河一葵がそうつぶやいて、マユカは視線を一葵に向けた。 「星河さんももバレンタインに興味あるの?」 「まぁ、気になるといえば気になるかな。でもオレ、バレンタインチョコってもらったことないんだよね…」 一葵はため息をつきながら言った。なんとなく、マユカは少し意外に思った。 「友だちとかは女の子からもらえなくても母親からはもらったりしてたそうなんだけど、オレ、母さんとはずっと一緒に住んでないから」 そういうことかとマユカは思った。 一葵はずっと母親の大空遥とは生き別れだった。1年と少し前に公にはなったものの、一緒には住んでいないようだった。 「去年はまだ女子の制服着てたし…。ってそういえば、去年は絵梨ちゃんに友チョコって言われてもらったっけ…」 そう一葵は言うと、複雑な表情になった。日比野絵梨からもらったといっても、友チョコではもらった実感がないのだろう。 ふとマユカは、自分がバレンタインチョコをあげたら一葵は喜んでくれるだろうかと考えた。 考えた瞬間に、なぜ自分はこんなことを考えたのかと恥ずかしくなった。別に、一葵にチョコレートをあげる義理などない。そう思って、マユカはバレンタインのことは考えないようにした。 放課後、クラスメイトの女子たちがチョコレートを買いに行っている間、マユカは寄り道をせずに真っすぐ家に帰った。ドアノブを回すと、鍵が閉まっている。 そこで思い出した。百貨店で働く母が、バレンタイン商戦で忙しいからと今日と明日は遅くなるといっていたことを。 そうして、マユカはカバンから、家の鍵を入れてある長財布をとりだした。その財布は、映画『砂の嵐』のオーディションで嵐(らん)役に選ばれた時に母から買ってもらったものだった。これからは一人前の女優になるのだからと、ブランド物の長財布を買ってもらったのだった。それからはずっと大事にその財布を使っており、家の鍵も財布の中にいれるようにしていた。 ただ、財布を買ってもらった時はうれしかったが、一つ欠点があった。大きすぎるのだ。手ぶらで買い物に行くことができず、カバンに入れて持ち歩く必要があった。 財布から鍵をとりだしてドアを開け、洗面所に入って手を洗って、リビングに行き、マユカは冷蔵庫のドアを開けた。今日と明日は晩御飯も適当に食べておいてほしいといわれたからだ。 冷蔵庫の中には特に何もなかった。カップ麺ならあるが、夜にカップ麺だけを食べる気はしなかった。 そう思ってマユカは、スーパーにいって晩御飯を買いにいくことにした。 一度、自分の部屋で制服を脱いで私服のセーターに着替え、買い物カバンを手に玄関にむかう。 「そうだ、忘れてた」と思って、一度部屋に戻り、学生カバンから財布をとりだして買い物カバンにいれた。 自宅を出て、10分ほど歩いて近所のスーパーに到着した。 弁当コーナーにいっておいしそうなものをさがす。カツ弁当や、チキン南蛮弁当があってどれもしそうであったが、カロリーが高かった。 迷った末、マユカは栄養大学が監修しているというヘルシーなお弁当を手に取った。ついでに明日の分も買っておこうかと思ったが、弁当の賞味期限は今日までだった。 まあ、明日は学校の帰りにでも買えばいいかと思い、マユカは弁当一つを買い物カゴにいれてレジに向かった。 その途中、バレンタインコーナーがマユカの目に留まった。板チョコが山積みになっている。 普段からスーパーで売ってる板チョコなんてあげる人いるのかとマユカは思ったが、よくよく見てみると『今年は手作りチョコを作りませんか?』と書いてあった。 簡単なレシピも書いてある。細かく刻んでボウルに入れ、湯せんにかけて溶かすらしい。 そこまでして手作りチョコをあげたいのか。下手に手作りにするより、そのまま食べた方がおいしいのではないか。 マユカはそう思ってその場を離れようとしたが、3歩進んだところで一度立ち止まった。 同時に、頭の中で一葵の顔が思い浮かべた。学校での会話を思い返す。バレンタインに興味はあるけど、今までチョコレートをもらったことがなくて残念がる一葵の顔。 チョコレートをあげたら喜んでくれるだろうかと再び考える。でも、手作りなんて重過ぎるし、そんな時間は…と思って思い出した。そもそも、今日は家に誰もいないので手作りチョコを作る時間は十分にある。 「ま、まあ仕事でお世話になってるし…。今までもらったことないのも可哀そうだし今年は特別…」 マユカは自分に言い聞かせるように一人そうつぶやき、板チョコを買い物カゴにいれた。 先ほど、家で見た冷蔵庫の中身を思い出す。バターや卵ならあったはずだと。 家に帰ったマユカは、さっそくエプロンをつけ、チョコレートを刻んだ。 湯せんにあてたボウルに、刻んだチョコレートとバターをいれて、泡立て器でまぜる。 まぜている最中、マユカは自分が無意識に鼻歌を歌っていることに気づいた。思わず恥ずかしくなったが、今は誰も家にいないのだと思いなおし、静かに再開した。 卵もいれて混ぜて、オーブンで焼く。30分ほどしてガトーショコラができあがった。 一度、マユカは味見をした。おいしい。思わず笑みがもれた。これなら喜んでくれるかもしれないと。 その後、ガトーショコラを作るのに使った道具を流しで洗い、両親が帰ってくるまでにすべて片づけた。親には変な詮索をされたくなかった。 次の日の朝、マユカは家を出ようとして念のため一度、学生カバンの中身をチェックした。カバンの中には、昨日作った手作りチョコが袋にラッピングされて入っている。 そのことを確認するるとカバンを閉め、もうすぐ仕事にでる母親にたいして「行ってきます」と言って家をでた。 さて、どうやって渡そうか。登校中、マユカは思案した。 どこかに呼び寄せて渡すか、さすがに恥ずかしいから机の中にでもいれておくか。渡す時のことを考えて、マユカはドキドキと心臓の鼓動が早くなるのを感じた。 と同時に、いやいや、何で緊張してるんだと頭を振り払った。普通に渡せばいいのだ。普通に、と。マユカは思い直した。 教室に到着してマユカは一葵の席を見た。まだ、一葵は来ていない。 マユカは一葵の隣の席に着席し、一葵が来るのを待った。1分が経過し、5分が経過する。クラスメイトは次々に教室に入ってくるが、一葵はまだ来なかった。 今日に限って、風邪で休みだったらどうしようという不安が頭によぎる。それなら、わざわざ手作りチョコを作った意味がなくなってしまう。 いや、そんなことはない。多分、大丈夫。そう思って再び、マユカはカバンの中を確認した。一葵が席に座ったら普通に「これ、あげるわ」と言って渡したらしい。多分、もうすぐくるはずだからと。 「おはよーっす」 その声でマユカは扉のほうに目をやった。一葵が登校してきたのだった。時計をみると、普段一葵が登校してくる時間だった。 一歩一歩、一葵は自分の席に向かう。 席に着くときにいつも通り挨拶して、そのまま普通に渡せばいい。マユカはそう思い、カバンの中に手を入れた。 そうして、一葵は自分の席の横までたどり着き、椅子を引こうとする。その時だった。 「一葵くーん!」 クラスの女子生徒の甲高い声が教室に鳴り響き、彼女は、一葵に近づいた。 「チョコレート、あげる!」 女子生徒はかわいらしい袋を一葵に手渡した。 一葵は驚きながら「えっ! ありがとう!」と言って、笑顔になった。 「これからも、応援してるね!」 そう言って、女子生徒は自分の席に戻っていった。 そのまま一葵は袋を手にもって、マユカにみせ「もらっちゃった」とうれしそうに言った。 いちいち、見せびらかさないでほしいとマユカは思った。思わずイライラしそうになったが、平静を装うようにつとめる。 「そう。よかったわね」 マユカのカバンの中には、手作りチョコの袋が入ったままだった。 4時間目の授業が終わり、昼休みになった。 今日は授業の中身がどうにも頭に入ってこないとマユカは感じていた。思い当たることは一つある。まだ、手作りチョコを一葵に渡せていないことだ。でも、どうしてこんなことで悩んでいるのかは分からなかった。 そもそも、今までもらったことがなくて可哀そうだからという理由付けで渡そうと思ったのだ。それができなくなってしまったら、もう渡す必要もない。 隣に座っている一葵は家からもってきたお弁当と、今日もらったチョコレートを机の上に並べてどうしようかと悩んでいる。 もうすでに、10人の女子生徒からチョコレートをもらっていた。中には、高そうな人気ブランドのチョコレートもある。 1年前から男として芸能活動を続けていた一葵は、マユカが思っている以上に人気になっていたのだった。 「こんなにもらっても食べきれないなー。マユカも少しいる?」 一葵のその発言にマユカは苛立った。 「バカじゃないの。あなたその言葉、チョコをあげた女の子に失礼だと思わないの?」 「ご…ごめん。そうだよな。」 マユカはイライラしながらもカバンをてにとって教室を出た。食堂でお昼ご飯を食べるためだ。普段は母にお弁当を作ってもらうことが多いが、今日は前日の仕事の疲れで食堂で食べてきてほしいといわれていたのだった。 イライラしてあまり食欲もないが、ご飯は食べなければいけない。 移動しながらもマユカはイライラがおさまらなかった。 世の中には学校にチョコレートをもってくると取り上げられる学校も多いというのに、なぜこの学校はOKなのかと。 自由な校風といえども、ここまで自由でなくていいではないか。渡すなら、もっとこっそり渡すべきだ。マユカはそう思った。 食堂について、メニューを見る。今、財布の中にいくら入っているだろうかと思い、マユカはカバンを開けた。 真っ先にラッピング袋が目に飛び込んできたが、それをのけて財布を探す。つづいて、カバンのポケットを探し、スカートのポケットに手を入れた。 「無い…」 カバンの中に財布が入っていないことに気が付いたマユカはそうつぶやいた。 いったいどこに…、と考えて思い出した。 昨日、買い物から帰ってきて財布から鍵をとりだしてドアを開け、そのまままた買い物カバンにいれなおしたのだった。 そこまで考えて、マユカはゾクリとした。家の鍵は財布の中だ。つまり、親が帰ってくる夜まで家に帰れないことになる。 放課後、あてもなく歩いていたマユカは、あまり子どもが遊んでいない公園を見かけて、そのブランコに腰かけた。 家に帰っても鍵がないから入れない。近くに頼れそうな人もいない。 マユカはため息をついた。吐いた息が白くなる。2月ということもあって、まだまだ外は寒かった。 なんてついていない日なのだろうとマユカは思った。 鍵をいれた財布は忘れるし、授業の内容は頭に入らないし、それに何より…。とマユカはカバンをおいて中を見た。結局、一葵にチョコを渡せていない。 なぜ朝、カバンの中を確認した時に財布が入っていないことに気づかなかったのだろうとマユカは思った。チョコにばかり気を取られて、財布を忘れる。しかも、結局そのチョコは渡せないままだ。 今日は、本当についてない。最悪のバレンタインだと思った。バレンタインにチョコを渡すなんて所詮、お菓子メーカーの策略。何でそんなものに乗っかってしまったのかとマユカは後悔した。 朝から何も食べてないマユカは、さすがにお腹がすいてきた。いっそのこと、自分で食べてしまおうかと思ってカバンの中に手をいれた。その時だった。 「あれ、マユカじゃん? どうしたのこんなところで?」 その声を聞いてマユカは、声のするほうを振り向いた。そこには、スーパーの袋を手に持った私服姿の一葵がいた。買い物帰りらしい。 「な、何でもないわよ! ちょっとブランコに乗りたくなって。そ、そう、あれよ。今度の役でブランコに乗る話があって…」 とマユカは少し語気を強めて言った。あまり困ってるような姿は見せたくなかった。 「それならいんだけど…。てっきりオレは、家の鍵を忘れて帰れないのかと。」 「なっ!?」 一葵の言葉に思わず驚いて、マユカは顔を赤らめた。 「あれ? もしかして当たり? そんな強がるなよ。オレも、たまに父さんが休みの時に鍵を家に忘れてでてしまうことがあるんだ。そんな日にかぎって、父さんパチンコで遅くなったりして。軽くパニックだよね」 同意を求めてくるような口ぶりで一葵は言った。一緒にしないでほしいとマユカは思ったが、同じかもしれないと思った。 「べ、別にたいしたことないわよ。夜には帰ってくるし、適当に時間をつぶせばすぐだわ」 マユカは強がるように言った。正直、この寒さでずっと外にいるのは辛いものがあった。でも、どうすることもできないものであった。 「それならさ…」 一葵は少し考えてからそう言って、続けた。 「ウチに来ない?」 何気ないことを言うように一葵は言った。 ただ、マユカとしては想定外の一葵の発言に顔を赤らめた。 「そ、そんな、悪いわよ急に…」 「大丈夫だって。父さんも今日は仕事で遅くなるから誰もいないし」 一葵のその言葉で、マユカはまた顔を赤らめた。今、一葵の家にいったら二人きりということだ。何を思ってそう言ってるのだとマユカは思ったが、多分何も考えてないのだろうなと思って、問いたださなかった。 「それに、今日、お昼も何も食べてないんでしょ? 食堂から戻ってくるのやけに早かったし」 「そ、それは…、今日は食欲がなかったからで…」 マユカがそう言うと同時に、お腹の音が鳴って、一葵は笑った。恥ずかしい。マユカはいたたまれなくなるほど恥ずかしかった。 「今日はカレーにしようと思ってるんだ。材料は十分あるから大丈夫。それにカレーはオレの得意料理だから、ちょっと自信あるんだ。」 何だそのアピールはとマユカは思ったが、確かに悪い話ではないとも思った。このまま寒い外で親の帰りを待つよりは、誰かの家で待たせてもらうほうがよっぽどかいい。 何よりマユカとしては、一葵の作った手料理を食べてみたいと思った。 「じゃ…、じゃあ、お言葉に甘えて…」 マユカはうつむき加減で小さくつぶやいた。 しばらくして一葵の家にあがったマユカは、一度家の周りを見渡した。一度、外から見たことがあったが、中に入ったのは初めてだった。 想像していたよりも狭い部屋だ。襖はボロボロで、一部テープで補強してある。いかにも貧乏な部屋といった感じだ。あの大女優、大空遥の子どもの部屋とはとても思えなかった。 「今でも、この家で暮らしてるのね」 マユカは、エプロンをつけた一葵に向かってそう言った。 「まあね。芸能人デビューしてお金貯まったらこの生活ともさよならしようと思った時もあったんだけど、なんだかんだで結構愛着あってなかなか離れられないんだよね。」 たしかにこの部屋は、貧乏な暮らしを感じさせる部屋ではあるが、その分、生活感を感じさせる部屋でもあった。ここで、一葵は暮らしているのかと思うと、マユカは感慨深かった。 「マユカはコタツにでも入って休んでてよ。テレビもつけていいからさ」 お鍋を棚から取りながら一葵はそう言って、マユカはコタツに入った。コタツの中は温かく、それだけで寒さも吹っ飛んだ。 普段、マユカの自宅では、暖房をつけるときはエアコンか床暖房をつけており、コタツに入ったのは初めてだった。話には聞いていたが、ぽかぽかして温かい。先ほどの寒い外の気温を思い返して、マユカはもうここから出たくないとすら思った。 テレビもつけていいと言われたが、テレビはつけないでおいた。その代わり、マユカは一葵が調理する音に耳を傾けた。 包丁で人参を切る音、お肉の炒める音、お鍋のグツグツという音。一葵の後ろ姿を見ながら、マユカは一葵の生活感を感じていた。 しばらくして「そろそろいいかな…」と一葵は言うと、お皿にご飯とカレーを盛り付け、マユカの前と、マユカの対面に置いた。左にカレールー、右にお米といういたってシンプルなカレーライスだ。 マユカは「いただきます」と言ってスプーンで一口分とり、そのまま口の中にいれた。甘口だ。 「今日もらったチョコを入れてみたんだ。でもちょっと、甘くなりすぎたかな…」 確かに少し甘いカレーではあった。だけどその分、優しい味わいだった。味もおいしいし、温かいカレーで心も安らいだ。 こういう生活も悪くないかもしれないとマユカは思った。貧乏ボロアポートで、生活に苦労することもあるだろうけど、好きな人と二人ならこういう生活も悪くないのではないかと。 しばらくしてカレーを平らげたマユカは、一度口の周りをティッシュで拭いて「ありがとう。おいしかったわ」と一葵に伝えた。 それを聞いて一葵は、「それは、よかった。」と満面の笑みで答えた。 マユカはその一葵な顔を見て、ドキリとした。やっぱり、自分が作ったものをおいしいと言ってくれることはうれしいのだろうかと。 そこで、マユカは思い出した。カバンの中に、手作りチョコのガトーショコラが入っていることを。多分、渡すなら今しかない。 そう思ってマユカはコタツから一度でて立ち上がり、一葵が皿洗いを終えて戻ってきたタイミングで、カバンの中から手作りチョコをとりだし、「これ、よかったら…」といって手渡した。 一葵は「えっ!?」驚いた顔をして、「くれるの?」と発した。まさか、このタイミングでチョコレートをもらえると思ってなかったのだろう。普通、渡すなら学校で渡すはずだ。 「そ、その、勘違いしないでよね! バレンタインにチョコをもらったことがないって言ってて可哀そうだからもってきただけ。ただ、今日はいろんな女の子からもらってたから別にいいかと思ったのよ。だからこれは、バレンタインチョコじゃなくて、カレーのお礼だから」 ラッピング袋を手に取った一葵は、すぐに袋をあけた。今ここで開けるのかとマユカは戸惑いながらも、何も言わずにいた。 「チョコケーキだ! 食べていい?」 一葵のその言葉でマユカは小さく頷いた。すでに一葵の手にはガトーショコラを掴んでおり、そのまま一口食べた。少しだけボロボロとガトーショコラのかけらが床に落ちた。 「うん。おいしい!」 一葵は満面の笑みでそう言った。とたん、マユカは心臓の鼓動が速くなるのを感じた。同時に、幸せな気分だった。狭い部屋で二人きり。今なら、なんでも伝えられるような気がした。 「そ、その…、あたし前から…、」 あなたのこと…、そう続けようとした時に、玄関から「ただいまー」と声が聞こえてマユカは我に返った。一葵の父、星河鉄郎が帰ってきたのだった。 「おや、珍しい。お客さんかい?」 「は、はい。お邪魔してます」 そう言ってマユカは鉄郎のほうに体を向けて頭を下げた。心臓の鼓動は速いままだ。 「父さん、ちょうどよかった。さっきカレー温めたところだから、すぐご飯にできるよ」 一葵がそういって、鉄郎は「そうか。じゃあ、今日は先にご飯にしようかな」といってコートをハンガーにかけた。 マユカは時計に目をやった。まだ母親が帰ってくる時間ではないけれども、ゆっくり帰るとちょうどいい時間だと思った。 「じゃ、じゃああたし、そろそろ帰るわね。もうすぐ親も帰ってくる時間だから」 マユカがそう言うと、台所に立っている一葵はマユカのほうに向きなおった。 「もう帰るの? じゃあオレ送ってくよ。外、暗いし」 「いや、いいのそれは!」 思わず強い口調になってマユカはそう言った。一度、気持ちを落ち着かせて言葉を続ける。 「お父さんの食事の準備があるんでしょ。あたしは大丈夫。それに今は、一人で帰りたい気分だから」 マユカがそう言うと、一葵は「そうなの? じゃあ、気を付けて」と答えた。 マユカは玄関で靴を履き、「おじゃましました」と言って、外にでた。 寒い中、マユカはゆっくりとした足取りで家にむかった。 ふと、先ほど自分は何を言おうと思ったのだろうと思い返した。あの時、鉄郎が帰ってこなかったら何を言おうとしていたのか。 なんとなく言わなくてよかったとマユカは思った。言おうとしたことが、本心かどうかさえ、マユカ自身、分からなかった。 外の気温は先ほどより寒くなり、雪もパラパラと降ってきた。あまりの寒さにマユカは手で口元を覆い、息を吐いた。先ほど食べたカレーの匂いがした。 その匂いで、マユカは一葵の笑顔を思い出した。カレーをおいしいと伝えた時の一葵の笑顔と、手作りチョコを食べた時の一葵の笑顔。 その笑顔を思い返して、マユカはほほ笑んだ。 今日は、最高のバレンタインだったと。掲載誌の都合上とわけかはわかりませんが、少女少年ってラブコメ漫画には定番のバレンタインに関する話が無いんですよね(そんなこと言ったら、小学五年生で連載されていた『EVE★少女のたまご★』にはあるだろと言われそうですが)。
で、それなら少女少年のキャラの中の誰かでバレンタインの話のサイドストーリーを書いてみようと思って書いてみました。
マユカと一葵の話は以前にも書いたことあるのですが(望月マユカ編~ライバルのあなた~)、この二人のカップリングは個人的に好きなので、また書いてみました。
相変わらず、タイトルには悩みます。今回は完全にミスリードのタイトルにしました。タイトルから受ける印象と全然違う終わり方なので、途中はタイトル通りなので、まあいいかと。