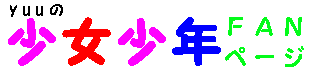第1話~謎の訪問者~
「今まで本当にありがとうございました」 大室哲郎の家の前の廊下。 そこで、3人の少年少女が大室にお辞儀をしていた。 その3人は今まで大室の家に居候しており、最近になってようやく3人だけで暮らす目途がたってきたためアパート暮らしを始めることになり、ここをでていくことになったのだ。 ちなみにこの3人、それぞれ兄弟で兄とその弟とその妹の3人である。 一昔前は、兄は女装して芸能界にいたのだが、声変わりもあってじょじょに芸能界を離れ、自然に引退した。 その代わりでてきたのが、弟と妹による小学生漫才コンビである。この二人によって、なんとか暮らしをたもっていけそうな状態であった。 また、最近は兄も新聞配達のバイトを始めたようで、さらに生活に余裕がでてくると考え、いつまでも血もつながっていない大室の家にお世話になるのもなんなので、ここを出ていくことにした。 「またいつでも遊びに来い。それと、下の二人は俺のためにももうちょっとがんばって働いてくれ」 「またあの肉じゃがが恋しくなったら来ます」 最後に弟がそういい残し、3人は大室の家から離れていった。 少し寂しくなるかもしれないが、これでようやく一人になれて気楽だ! そんなことを思いながら、大室が部屋に戻ろうとしたその時、 「おいおっさん」 そんな声が大室の耳に届いた。 まあ、自分のことではないだろう。そう思いながら気にせず入ろうとしたのだが、 「呼んでるだろうが!」 そう言われて、大室の腕を強引につかまれた。 ――ったく、なんだよ急に・・・ そんな風に思いながら大室は声の下方向を振り向いた。 別にたいしたことはない、どこにでもいそうな男の子がそこにいた。 少しかわいらしい雰囲気もあるように見える。 しかし、大室はその少年を見たことすらなかった。 「誰きみ?」 そう言うや否や、その少年は大室の前で土下座をし、言った。 「俺を、俺をここに住まわせて女として芸能界に入れさせてくれ」 いきなりのことである。 一瞬、大室は目の前の少年が何を言ってるのか分からなかったが、心当たりはあった。 なぜか、大室の事務所では今まで、女と偽って何人もの少年を芸能界デビューさせてきた。 きっと、この子はそれを知っているのだろう。 「とりあえず、中に入ってから話そう」 そんな話を廊下で話していて誰かに聞かれたらまずい。大室はそう判断して、その少年を部屋の中に入れさせた。 少年をリビングの椅子に座らせ、大室はカップにコーヒーをそそぐ。 少年は先ほどから下を向いていて、大室にはどこか震えているような気がした。 「で、何で女装して芸能界に入りたいんだ?」 「家出だよ」 ずいぶん率直だ。 家出するぐらいだ。多分ちょっとした不良なのだろう。 大室は落ち着いて話をすることにした。 「名前は?」 「そうだな・・・片橋マヤなんてどうだろう?」 「いや、そうじゃなくてだな。本名だよ」 「片橋マヤ」 自分で本名ではないと言ったようなものなのに、それを本名と言ったこの少年はカップに口をつけた。 やはり、少しコップが震えているような気がした。 もしかして、虐待されてるから逃げてきたのだろうか? そんなことを大室は思いながらも、もう少し話を続けてみた。 「何で家出なんかしたんだ?」 「家出っていうかな・・・捨てられたって言ったほうがあってるかもしれねーな」 捨てられた・・・ね・・・ それにしても、本当に自分から何も話さない子だ・・・ 大室はそう思った。難しい年頃かもしれないが、いきなり他人の家に押しかけて、自分のことをあまり話さないなんて。 「女として芸能界に入らせてほしいって俺に言うっていうことは過去の例を知ってるってことだよな?誰だ?」 「それは、教えられない」 なぜそんなことまで教えられないのか分からないが、とりあえず大室は言っておくことにする。 「とにかく無理なもんは無理だ。家を出たいのなら俺のところではなく、警察にでも相談してくれ」 「そこにはもう行った」 話が続けにくい子である。 「とにかく無理なもんは無理だ」 「じゃあ何であいつは・・・」 「あいつって? さっき出て行ったあいつのことか?」 大室が言ってるのは先ほどの兄弟の一番上の兄のことである。 なぜか数秒、静まり返った 「あ・・・ああ」 大室の目の前で少年は言った。 少し考えてから言ったらしい。 ということは多分、この少年が言ってるアイツとは先ほどの兄弟のことではない。 実は言うと、昔にもう一人大室と居候していた少年がいるが、そっちのことを言ってるのだろうか? 「どうすりゃここに住ませて、女装して芸能界に入れさせてくれる?」 どうしようにも大室は入れさせる気はない。 だいたい、女装して芸能界に入れさせようにも声変わりしてそうな声だし、顔・・・は、まあギリギリ大丈夫か? 女装したら10代後半の女性ぐらいに見えなくもなさそうである。 そういや、年齢を聞くのを忘れていた。 「年齢は?」 「10代だ」 んなもん見たら分かる! と大室は言いそうになったが、止めておいた。言ったところで、実年齢は言うつもりないのだろ。 見た感じでは、中学生ぐらいだろうか? とりあえず大室は、これ以上何を言っても帰ってくれそうにないので、少し考えた末、チャンスを与えることにした。 「明日、とある映画のエキストラオーディションがある。それに合格したら考えてやってもいい」 「今日は? 後、ヅラ」 「今日だけは泊まってもいい。ウィッグは貸してやる」 「ありがとうございます」 お礼はできるそうだ。 ちなみに、明日のオーディションとは大室とはほとんど関係ない。 映画制作会社が直接主催するオーディションで、全国の事務所に広報だけ知らせてあり、大室はふとそのことを思い出したのだ。 とりあえず、その日は適当に寝巻を貸して泊まらすことにした。 そして次の日。 7時に目を覚ました大室であるが、すでに少年は起きているようである。 少年はベランダに出て遠くを見ていた。 「どうしたんだ?」 大室は後ろから呼びかけた。 「いいや、それにしてもいいトコにすんでますね」 「ありがとう。それにしても起きるの早いな」 「ええ、こういう習慣をつけられたんで」 とりあえず大室は今日の予定を一通り少年に教えた。 部屋から、ウィッグを持ってきてかぶせる。 まあ、10代後半のかっこいい女性といったところだろう。 今日のエキストラオーディションも女子高生役だからちょうどいい。 それより、ここにきて大室は大変なことを忘れていることに気づいた。 「それより君、女の声だせんのか?」 少年は大室からそう言われ、ひと言こう言った。 「片橋マヤです」 それはそれは、透き通った女声であった。 「どこからそんな声だせるんだよ」 「このために1年間特訓してきました」 そこまでして女装して芸能界に入りたいのかよ! という突っ込みはしなかった。どうにも突込みをしたら、場がしらけそうなキャラなような気がするからだ。 その後は、簡単な朝食をすまし、大室は少年を車に乗せ、オーディション会場にむかった。 今回のオーディション、エキストラとはいっても端役という少しは物語に重要な役割をする人を決めるオーディションである。 内容は、主役の女子高生が廊下を歩いてる最中、その近くで噂をするという役。 そこまで言うほど難しくないかもしれない・・・。それほど演技力が必要なわけでもなさそうだ。 もしかしたら、何かの間違いで受かってしまうかもしれない。 今さらながら大室は少し後悔してきた。 しばらくすると会場近くの駐車場に到着。 会場に入り、受付をすまして辺りを見回して参加者を、見てみるとそんなに多くない。 運よく通る可能性も十分考えられた。 「えっとじゃあ、これからどうするか簡単に説明するから君・・・」 「名前で呼んでください。片橋マヤです」 マヤは静かに言った。 「OK分かった片橋。まずはそこの受付で名前を書いて・・・」 それからマヤは一人で大室の指示通りに行動をし、番号札を受け取った。10番である。 大室は保護者席に座っていた。 「おや、大室さんじゃないですか」 この映画のプロデューサーに大室は声をかけられた。 「どうも、お久しぶりです」 「あなたの事務所のかたもこのオーディションに?」 「いや、昨日僕のもとに女の子がやってきましてね。とにかく芸能界に入りたいといいだしてきまして」 「それで、今回のオーディションに?」 「はい、出来次第によっては事務所に入れるか考えると言ってしまったので」 「そうですか・・・では、審査員側の席に椅子を用意しますので、見て行きますか?」 「そうさせていただきます」 大室は審査員席の端に座った。 どうやら、もうすぐ始まるようである。 オーディションの内容はまずは、番号の早い番号の人が話し役になり、遅い番号の人が聞き役になる つまり、まずは1番と2番の人間がでてきて1番が噂を話す役。2番がそれを聞く役。 次に、2番と3番がでてきて、2番が話す役、3番が話す役と順番にしていく。 どうやら、オーディションに出る人数は10人だけらしく、確率でいうと5人に一人、つまり5分の1の確率である。 オーディションが始まった。 だいたい、まだ芸能養成学校に入ったばっかりの子や、入ってもいない子が多いのだろう。 緊張していたり、大げさすぎたり、ひどい子なんて棒読みである。 さて、マヤの最初の出番がやってきた。 9番が話し手、10番が聞き手である。 話の内容は、学校の怖い話。 話し手が怖い話をして、それを聞いてる聞き手が「やめてよ。」とか「やだ。」とかただそれだけの内容である。 「昔ね、この学校の屋上で自殺した女の子がいてね・・・」 そんな会話から始まる。 さて、マヤの最初の台詞がやってきた。 「えっ? それホント?」 先ほどから眠そうにウトウトしながら聞いていた大室であったが今の言葉で目が覚めた。 マヤの言葉はさきほどからやっているオーディションの子と全く違ったニュアンスが感じられたのである。 怖がってはいるのだが、続きも聞いてみたいというのがひしひしと伝わってくる。 どうやらそう感じているのは大室だけではないらしい。 審査員も先ほどのマヤの言葉で目の色が変わった。 さて、その回は終わって最後のオーディションである。 話し手がマヤ、聞き手が1番となる。 「昔ね、この学校の屋上で自殺した女の子がいてね・・・」 先ほどの子と台詞は全く一緒なはずである。 しかし、大室はどこか会場の空気が変わったような気がした。 台詞は徐々に終わりに近づいていく。 「そして、夜になって音楽室から音が聞こえたらしいの。ピアノの音が」 さて、今は冬だっただろうかと大室は考えた。 先ほどから鳥肌がたっているのである。 「気になって音楽室のドアを開けた見回りのおじさんはそこで見たのよ!」 「もうやめて!」 「誰もいないのに、動いてる鍵盤から垂れている血を・・・」 そこでオーディションは終了である。 なぜか1番の少女は半泣きになっていた。 しかたがない、マヤは真剣な目つきで1番の表情を見ながら、素晴らしい演技をしたのだから。 パチパチパチ どこかから拍手の音が聞こえた。 プロデューサーである。 つづけて、他のスタッフ、つられて他のオーディション参加者も拍手をした。 今まで、そんなことはなかったというのに。 結果は、後日ということらしかった。 どう考えても、当日でもよさそうなものなのに。。 「それまで泊めさせてもらえませんか?」 マヤは大室の車の助手席でそう言った。 「ああ、合格だろうしな」