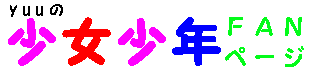第6話~夕焼け観覧車~
拓海とゲーセンに行ってから3日たった今日。 愛梨と出演した携帯電話のCMがシリーズ化することになり、今日と明日にその撮影がある。 すなわち、今日は愛梨と会うことができるのだ! そして、今日は愛梨に言うことがある。初デートの申し込みだ。 前回は仕事だから無理ということだったものの、今回は事前に愛梨のマネージャーから仕事が入っていないことは確認済みだ。 でも、これで「仕事だから無理」とか言われたらどうしようか・・・。もし、俺に気を使って告白にOKをしてくれているのだとしたら、そう言われてしまうこともありうる。 いや、いやいやそれはない。それはないはずだ。ネガティブ思考になるな俺。 「あの~」 いろいろ考え事をしていると、後ろから愛梨の声がした。いつのまに・・・。 「ごめんね。そろそろ着替えようと思って」 ここは控え室兼更衣室。愛梨が着替えるということは俺はこの部屋から出て行かなければいけない。 が、しかし今日はまず言いたいことがある。帰りのほうがいいかもしれないが、タイミングを逃す可能性もある。 そして、「愛梨、その前にお願いがあるんだ。」と前置きしたうえで、今度の日曜日のデートの申し込みを愛梨にした。 愛梨はしばらく考える素振りを見せた後、こう返した。 「ごめんなさい」 なーーーーーー! や、やっぱり俺に気を使ってOKしてくれただけだったのかーーー! そうか。そうだったのか・・・。気を使わせて悪かったよ・・・。 「その日は予定が入るかもしれなくて。学校の友達と遊ぶ約束をしてて・・・」 え・・・・・・。 な、なんだ友達と遊ぶ約束をしてるのか。残念だけど、先約があるなら仕方ない。 「そうか、じゃあまた今度・・・」、と言いかけた時、愛梨は言った。 「え、えっとそれが、その子まだ予定がはっきりしてないみたいで、明日なら分かるようだから、明日返事させて」 とのことであった。 次の日の学校での昼休み。 俺は次のデートについて考えていた。 デートの場所はいつものゲームセンターがあるあの場所。飲食店もあり、洋服店もあり、行ったことはないけれども最上階には映画館もあったはずだ。 途中、ゲーセンによって俺のゲームテクニックを見してもいいかもしれない。「すごい!素敵!」ってなっちゃったりして・・・。 そしてなんと言ったって、屋上に併設されている観覧車。ラストにその観覧車で二人きりでのって・・・。ムフフ。妄想が広がる・・・。 ってまあ、まだ決定ではないのだけれども。 「なあ友樹」 いろいろ考え事をしていると、後ろから翔太の声がした。いつのまに・・・。 「今度の日曜日、久々にゲーセンでもどう? そろそろ受験勉強に専念しなきゃいけないから、これを逃すと遊ぶ機会当分なさそうなんだけど」 何かと思えば、久々に翔太からのゲーセンの誘いであった。ここしばらくは全くなかったのだけれども。 「そうだな。当分遊ぶ機会ないならパーっと・・・」 と言いかけて思い出した。日曜日は愛梨とデートの約束をした日じゃないか。 まだ、決定とはいえないとはいえ、俺がここで翔太と遊ぶ約束をしてしまうのはどうなんだ・・・。 さすがに、三人で遊ぶという選択は選びたくないぞ・・・。 でも、でも当分遊べないか・・・。うーん・・・。 「悪い。日曜日は先約が入ってて・・・」 「何? また仕事か?」 「いや、仕事じゃなくてさ・・・。その・・・。デートなんだ・・・」 なぜかここで、翔太は黙りこむ。3秒、4秒、5秒・・・。 「そうか。なら仕方ないな」 うっ・・・。なんか罪悪感が・・・。 「楽しんできなよ」 「ああ・・・。ありがとう」 俺の罪悪感をよそに、翔太の顔はどこかすっきりしたような顔であった。 日曜日になった。 結局、愛梨は友達との約束はなくなったようで、無事に今日は初デートの日となった。 それにしても、先日の翔太の言葉がどうにも気がかりだ。 先約が入ってたとはいえ、当分遊べなくなるかもしれない友人の誘いより、すぐにでもできるかもしれないデートを優先したんだから。 まあでも、来週はいよいよファイモンの発売日だし、発売されたら翔太とはめいいっぱい遊ぶことにしよう。今年いっぱいは大丈夫みたいなこと言ってたし。 「お待たせ」 と、翔太のことを考えていたら愛梨がやってきた。 俺は友美として仕事するようになって、ティーンズファッション雑誌なるものを時々読むようにしているのだけれども、愛梨はそんな雑誌にでてきそうなかわいい服装であった。 「かわいいよ」 やばい。俺なんか言った。俺基準で超絶かっこいいこと言ってしまった。 「ありがとう」 自分で言っといて恥ずかしくなるギリギリのところで愛梨はお礼を言ってくれた。照れてる愛梨がまたかわいい。 よし。とりあえずデート開始だ。初デートで幻滅されて振られることもあるらしいし、そこは慎重に。 「どこか行きたいところある? 一応、映画館があるみたいだから映画でも見に行こうかなって思うんだけど」 「うん。おまかせするね」 というわけで二時間ほど映画館で時間をつぶすことにした。 学園モノのラブストーリーで、お互い好き同士の男女が勘違いなどのすれ違いで、なかなか相手に思いを伝えられないものの、最終的にはなんとか二人の誤解が解け、はれてカップルとなるという話で合った。 CMで散々、「こんな泣ける映画は初めて」だとか「涙が止まりません」だとか宣伝していた映画だけれども、いったいどこで泣けばいいのかはわからなかった。 第一、つまらない。 一応、ここに来る前に調べてみたのだけれども、女性には人気らしいとのことであった。 男の自分が見ても面白くないのは当然なのか。 愛梨はどうなんだろか。面白いと思ってくれただろうか。と思って聞いて見ることにした。 「ごめんなさい。もう一つだったかな」 愛梨はパスタをフォークで回し取りながら、そう答えた。 ここは先日、拓海と入ったパスタ店。まあまあおいしかったので、今日もここに入った次第だ。 って、っそんなことはともかく、愛梨の感想だ・・・。もう一つだったか・・・。 まさか。それなりに評判の映画を選んで失敗だとは・・・。こんなつまらない映画を選ぶなんて信じられなーい。なんて思われてないだろうか。 いや、いやいや、そんなことはない。 だいたい、こないだもテレビで見たけど、意外と好き同士より嫌い同士で話があったほうが進展するらしい。ここはむしろチャンスじゃないか。 「やっぱりそうかぁ。俺もそれなりに評判よさそうだから選んだだけだけど、失敗だったよ。そういえば、普段はどういう映画を見てるの?」 「うーん。SFとか好きかな。」 「SFかぁ」 ありゃ。SFか。 俺も翔太の影響でそっちのジャンルのほうがよかったし、今度はそっちにしよう。帰ったらチェックだ。 ふと何気に、店内のテレビを見てみると、ちょうど拓海がでており、司会者と何か話しているところだった。 「芸能界にいると、周り可愛い子ばっかりだから好きな子とかできたんじゃないの?」と、司会者が拓海に聞く。 拓海は少し戸惑いながらも、「ええ・・・まあ・・・」と答える。 「仕事で知り合った子?」 「はい。実は先日その子と一緒に・・・」 と、拓海が何か言おうとしたと同時に、俺は「じゃあ、そろそろ出ようか」と愛梨に促した。 店をでて次はどこに行くか。 先日の俺みたいに、愛梨がパスタで服を汚すなんてことになれば、洋服店にでも行くつもりでいたが、残念ながら愛梨はかなり丁寧にパスタを食べたせいで、服が汚れることはなかった。 まあ、普通汚れ無いか。むしろ今日も俺のシャツが点々と汚れてしまったような・・・。 とりあえず、迷った末、個人的に一番行きたいところに行く事にした。 ゲームセンターだ。 「ちょっと見てて」 と言って格闘ゲームにコインを投入。バトル開始。 俺の素早い手さばきにより、あっという間に相手を倒すことができた。 そこで愛梨の顔を見てみる。「すごーい」なんて言ってもらえないだろうかと期待して。 が、愛梨は何か言いたそうにして迷っているような表情をしていた。 ふと、冷や汗を背中に感じる。 やばい! よくよく考えたら、格ゲーに縁もゆかりもなさそうな女の子が、格ゲーのテクニックを見たところでどう答えればいいのか分からなんて当たり前だろ! アホだ俺。最高にアホだ。 もう一つゲームするつもりだったけど、他のゲームに移った方がいい? いや、むしろゲーセンを出るべきか・・・。 と思っていると、愛梨が一言。 「私も・・・」 「えっ?」 「私もやっていい?」 なんというか、愛梨の発言には予想外の言葉が発せられることがよくある。それとも、俺が被害妄想なだけか。 「うんいいよ。隣で一緒に対戦もできるから、えっとこのボタンで・・・」 と言って簡単に操作方法を説明し、二人で対戦することになった。 まあ、さっきすごいテクニックを見せてしまったところだけれども、初戦は少し手を抜くことにしよう。 と思いながら、目の前の機械から「FIGHT」という掛け声が聞こえ、試合が始まった。 20分後。 この気持ちはなんと言い表わせればいいのだろうか。 評判がいい映画を見に行ったら、全然つまらなかったとかそういう次元じゃない。 いや、まどろっこしくいうのはやめよう。 先ほどからなかなか勝てないのだ。 正確には、勝ったとしてもギリギリでの勝ち。 まさか、発言以外でも予想外な展開になることと思わなかった。 俺はこのゲームの大会にもちょくちょくでることはあるのだけれども、少なくとも俺と同い年で俺より強い奴はなかなかいない。 翔太でなんとか俺と同じぐらいの強さだ。拓海は上達は早いとはいえ、俺のレベルにはまだまだだ。 それが、まさかこんなところにいるなんて・・・。しかも数少ない女の子で・・・。 「えへへ。実は前からよくやってて」 「そ、そうなんだ・・・」 正直、悔しいので後何戦かやりたかったのだけれども、それはそれで大人げないようなきもしたし、よけい悔しさが増しそうな気もしたので、ゲーセンを後にした。 それからは洋服店で愛梨の服を買い、これからもっと有名になるということも願って、変装用のお揃いの帽子とサングラスも購入した。 なんだかいろいろあった一日だったけど、まあ初デートにしてはよかったんじゃないかと思う。 映画はつまらなかったけど、愛梨はさほど気にしていないようだし、格ゲーに見せ場はなかったけど、愛梨はすごい楽しそうであった。 ところで、時間も時間なので、今はデートのラストを飾る場所にいる。 観覧車だ。現在、観覧車のゴンドラ内。だいたい45度ほど回ったところにいる。 俺は、今日を振り返りながら、外の景色を眺めている愛梨のほうを見てみる。 外はもう夕焼け空。 夕日色に染まった愛梨が愛おしいほどキレイだ。 なぜか、胸の鼓動が早くなる。 いや、なぜ早くなってるのかは分かる。でも、実行する勇気がない。 ここは二人だけの密室。 ゴンドラはゆっくりと天辺を目指す。 やるなら、夕焼け色に染まったこのゴンドラ内がいい。 決めた。 「愛梨!」 俺の呼びかけに、外を見ていた愛梨はこちらを振り向く。 それとほぼ同時に俺は愛梨の肩に手を乗せ、ゆっくりと愛梨を引き寄せ、俺自身も愛梨に近づいていく。 徐々に、俺と愛梨との距離が近づく。 50cm、40cm、30cm、20cm、10・・・ 「ダメ!」 と、愛梨が叫んだかと思うと、俺は愛梨に突き飛ばされた。 「き、キスはダメ・・・」と、横を向いて愛梨はつぶやく。 や、やっちまったー! すぐに俺は自責の年にかられ、体中から冷や汗がでているのを感じた。 いや、なんだかものすごいいい雰囲気だと思ったんだよ。夕焼けで照らされた密室のゴンドラ。 いやいや、雰囲気はよかったんだ。俺があんな行動をとるまでは。ああ、バカだったよ俺が。 「ごめん」 俺がそう言った時に、ちょうどゴンドラは天辺になるところだった。 後、半分もあるのかよ・・・。 観覧車から降りてもお互い気まずいせいか何もはなさず、結局駅まで送った後、「じゃあ、今日はここで」というなんだか切ないお別れの挨拶でデートを終えた。 俺は外回りのホームに立ち、反対側の内回りのホームには愛梨が立っているのが見えた。 電車がもうすぐ来るというところで、愛梨はこちらに手を振ってくれた。 こちらもすぐさま手を振り替えすが、すぐに電車で隠れてしまった。 電車に乗り、家の近くの駅を目指す。 これから愛梨とどう接していけばいいのだろうか。今までどおり接していいものだろうか。 頭のなかはそんなことばかり考えていた。 ふと、携帯電話が震えているのに気づいた。 母からのメールだった。駅の近くのスーパーで牛乳を買ってきてほしいとのことだ。 こんな時に・・・。駅から近いっていっても、家と逆方向だし・・・。 仕方がないので、スーパーで牛乳を買う。その後、駅を抜けて家へ帰ろうとする。 とそこへ、改札から出てきた人ごみの中に、見知った顔を見かけた。翔太だ。 むこうもすぐにこちらに気づき、こちらに駆け寄ってきた。 「おぉ! どうだったんだよデート? って聞きたいところだけど、その表情じゃあまりうまくいかなかったっぽいな」 えぇぇ・・・。俺、今そんな分かりやすい顔してるのか・・・。 「まあ、そうだな・・・。そんなところだ。翔太はどこ行ってたんだよ?」 「塾だよ塾」 「塾? あれ? 休みなんじゃなかったっけ?」 「えっと、あれだ。自由参加型だったんだよ」 塾ってそんな時もあるのか。塾に行ったことがない俺からしてみたら未知の世界だ。 「それにしても、お前落ち込み過ぎだぞ。無理やりキスしようとして失敗したか?」 「なっ!? 何で分かったんだよ!」 「お前とは長い付き合いだからな」 って言ったって、付き合った経験があるわけでもないお前に分かるのかよ・・・。 とは思ったものの、このまま自分の胸の内だけに留めておくのも辛かったので、相談することにした。 「・・・。やっぱり失敗だったよなぁ・・・。これからどんな顔してあえばいいんだろうって、電車の中でずっと考えてて・・・。」 しばらく沈黙が続く。 「いいんじゃないの。いつもどおりで」 沈黙を破ったのは翔太のほうであった。 「きっと相手も同じ気持だと思うぞ」 「そうだろうか・・・」 「初デートだったんだろ? 失敗の一つや二つしかたないって考えて、これから経験を重ねていけばいいじゃないか」 しばらく俺は考える。 「そうかもしれないな。ありがとう翔太。」 翔太のおかげで少し気分が晴れたような気がする。やっぱり、話をしてよかった。 でもなんだろう。何か別のことで心の中に何か引っかかっている気がする。 デートのことじゃない気がする。いったいなんなんだ・・・。 「じゃあ、俺家むこうだからここで」 「あ、ああ・・・。じゃあな。また明日学校で」 結局、その心の引っ掛かりが何かは、その時にはまだわからなかった。