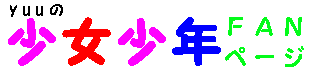第2話~謎の実力~
先日のオーディションの合格通知が届いた。 「こんなことってありえるのかよ・・・」 ふと、大室は合格通知を見て呟いた。 大室にもこんな経験は初めてなのである。 エキストラオーディションに出て、主役のライバルに抜擢されるなんていう子を見ることは。 確か、この役はもう決まっていたはずである。 今人気急上昇中のタレント、吉川夏樹だったはずだ。 なのに急に変更になるなんて・・・。しかも、病気とかの影響ではなく、監督とプロデューサーの意向で。 さすがにこれは、後々のことも考えて断ったほうがいいのではないだろうか? ふと大室はそんなことを思った。 急に変更なんかになったら、前から決まっていたほうのファンや本人などからひどい仕打ちがあう可能性がある。 たとえば、靴に画びょうを入れられたり・・・。 と、そういう可能性があることを言ったうえでマヤにどうするか尋ねてみた。 「だから何だよ。オレはオレの実力が発揮できる場所に出れれば文句はない」 とのことである。 大室には、その時のマヤの表情がまるで、断れば殺すとでも言いたげな表情のように見えた。 本当に悪役にはぴったしかもしれない。 それから1ヶ月ほどの月日が過ぎ、新聞、雑誌、テレビにと、あちこちのマスコミ業界でもともとの役者から 片橋マヤという名前も知られていない素人に変更になったというニュースが話題を呼んだ。 吉川夏樹がそもそも、今絶好調のタレントだったというのもあるだろうが、このニュースは1週間ほどは話題にあがった。 いったいどんな人物なのか! 過去の経歴は! などとマスコミが疑問に思うのも無理はなく、大室はマスコミの質問に追われる毎日が続いた。 そのたびに大室は自分の昔話で誤魔化していた。 「そもそもその話をするには、まず私がなぜ芸能プロデューサーになろうと思ったところから話さなければいけません。あれは、中学2年のある夏休み・・・」 「それより、片橋マヤのことを!」 「そう。マヤだ。私はその当時、ガラスの仮面を読んで・・・」 という具合にである。 だいたい、大室自身もマヤのことを全く知らないのだ。 とはいっても、どうせならそのまま、謎の少女として売り出したほうがいいのではないかというのも理由の一つであるが。 もちろん、マヤに注目したのはマスコミだけではなく、業界の人間も注目している。 そのため、CM依頼や一度うちのオーディションを受けてほしいなどの話がジャンジャン入ってきた。 「こんなに忙しいのは久々だ」 「・・・・・・」 マヤは無言でベランダから遠くのほうを見ていた。 いったい何を見ているのやら・・・。 大室はそんなことを疑問に思いながら、マヤのスケジュールを作っていった。 なぜか、acのCMとかあってそうだと大室は思った。 そして、マヤはどんどん仕事を増やしていき、さらに、かっこいい女性や演技力、謎めいた部分が魅力ということもありファンもどんどん増えていった。 テレビをそれなりによく見る人にしてみれば、マヤを見ない日なんてほとんどないというほどである。 胸はないが、背が高くスタイルがいいということもあってファッション雑誌などにも進出していった。 もはや休みなどないに等しく、大室は寿命が縮んでいくのが感じ取れた。 まさに、死語でぷよぷよぐらいでしか聞かないが、「ばたんきゅ~」といった感じである。 そんな中、マヤは何一つ文句を言わず、むしろ休みを入れようとすると大室を睨むほどであった。 しかし、仕事以外の場所では表情一つ変えず、笑おうとも怒ろうともしなかった。 時々睨んだりすることはあるがそれ以外はたいてい無表情である。 「一度家に帰ったらどうだ?」というヒマさえ与えなかった。 むしろ、それが狙いなのかもしれない・・・ そんな中、大室が一番断りたいと思った仕事の依頼がやってきた。 なんと、吉川夏樹と一緒のバラエティー番組にでるということである。 多分、この番組のプロデューサーもわざとこの二人を一緒の日にゲストに呼んだのだろう。 残念ながら、大室はこの依頼が来たときは他のゲストが誰だか知らず、いつものようにOKしてしまっていた。 しかし今さら何を言っても遅い。 なぜなら今は、本番30分前だからである。 マヤのほうはというと、いつものように準備万端であった。 一応、マヤにも吉川夏樹の名前を言ってあるのだが、誰それ? と言った感じであった。 最近、人気の人物だというのに。 ところで、芸能デビューするにあたり、ある程度芸能界の常識を教えておこうと大室はしたのだが、マヤはつい最近の芸能情報には疎いようであった。 よく知っているのは1、2年ほど前の情報。 本当に謎である。 「そろそろ本番入ります!」 スタッフの声がスタジオに響き渡った。 大室は壁際に立ち、見学することにした。 ところどころに、「こりゃあ今までで一番の数字とれるんじゃないか?」というような声が聞こえてきた。 本番が始まった。 二人とも普段のように普通にやっている。 特に、マヤのほうは吉川夏樹のことなど全く気にもとめず、司会者やカメラのほうばかりを見ていた。 しかし、吉川夏樹のほうは少しマヤのほうをちらちら見ているようである。 睨んでいるといったほうがあってるだろうか。 カメラは先ほどから吉川夏樹とマヤばかり映しているようだ。 これじゃあ、視聴者から見ても吉川夏樹がマヤを気にしてるというのがバレバレであろう。 で、これをネタに芸能ジャーナリストや芸能リポーターがコメンテーターとなっていろいろ話をするのだろう。 とりあえず、大室は関西の知人に頼んでそういう番組を録画してもらおうと考えていた。 東京じゃあ、そういう番組が少ないのが残念だ。 収録が始まって1時間30分、たいした問題はなくどうやら番組の収録は終わりになったようである。 マヤはまるでプログラムに指示されたとおりにしか動かないロボットのように立ち上がり、スタジオを出ようとした。 のだが、「こんにちは」という誰かの挨拶に引き止められた。 吉川夏樹である。 「ちょっといいかしら?」 スタッフなどその場にいる人の何人かは二人のほうを見、「おおーっ!」という歓声をあげた。 マヤは仕方なく吉川夏樹の言われたとおりにし、二人で人があまり来ないトイレに入っていった。 大室はとりあえず、『危険を察知したらオレに電話しろ』というメールをマヤに送っておいた。 「用があるなら早くすませてくださいね。私この後も仕事入ってるので」 マヤはトイレの壁にもたれながら吉川夏樹にそう言った。 「それが先輩にたいする態度? この業界ではそんなことじゃやっていけないわよ」 「すみませんね。これでもかなり気をつかってるつもりなのですが」 「だいたい、あなた私にひと言いうことがあるんじゃないの?」 「あなたとは今日が会うのが初めてですよ。何も言うことなんてありません」 「本当にそう思ってるの?」 マヤは今、壁にもたれかかりながら、少し目線を下げている。 その状態で、吉川夏樹の顔を見上げ、せせら笑うようにこう言った。 「ひがみ・・・ですか」 窓から冷たい風が吹いてきた。 「私があの役に選ばれたのはあなたより実力があると監督やプロデューサーに認められたからですよ」 吉川夏樹は硬直していた。 「まあ今日のあなた見ていたら分かりましたよ。本番に入っているというのに私のほうを気にして・・・」 「うるさい」 「あなたなんかちょっとかわいいだけでうれただけ。演技の『え』すら分かってるか疑問です」 「黙りなさい」 「あなたが売れたのは実力じゃなくて運じゃないんですか?」 「黙れって言ってるでしょうが!!」 トイレの外にまで聞こえそうなほどの大きな声で吉川夏樹は叫び、両手でマヤの首を絞めた。 「黙らないとこの口から何も言えないようにしてやるわよ」 吉川夏樹の顔は真剣であった、そしてマヤはその顔を見て笑った。 パシャ どこからか、カメラのシャッター音が聞こえてきた。 マヤの右手にある携帯電話からである。 「ちょっと・・・やめて、それだけは」 そんなことを言いながら、吉川夏樹は一生懸命にマヤの携帯電話を取ろうとしていた。 しかしマヤは上手いぐあいに手を引っ込め、取られないようにし、数秒後、マヤは右手だけで吉川夏樹の首を絞め、左手に携帯電話をもってこう言った。 「文句なら私にではなくて監督やプロデューサーに言ってください。吉川夏樹さん」 マヤはそう言い残し、トイレから出て行った。 トイレには腰が抜けてヘナヘナになった吉川夏樹だけが残った。