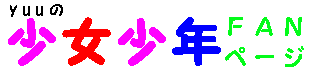第3話~謎の過去~
「今大注目のティーンアイドルねぇ・・・」 大室はとあるティーン雑誌を見ながらそう呟いていた。 ここ数ヶ月でマヤの人気は爆発的に伸び、どの雑誌を見てもマヤが載っているという状態にある。 おかげで事務所の通帳の額が指数関数的に増えていっている。 普段の大室なら、もし自分の事務所のタレントがここまで売れているなら言葉にできないほど喜んでいるだろう。 だが、なぜか大室は今回ばかりは素直に喜べないでいた。 「もっと喜んでくださいよ」 隣でマヤが言う。 大室はその言葉については何も答えず、話を切り替えた。 「大変だが、今度ドラマ出演の依頼が来た。どうやらメインヒロインらしいぞ」 「へぇー。どんな役なんですか?」 「よく分からんがいじめドラマらしいな。お前はいじめられっ子の役だ」 「いじめられっ子・・・ねぇ・・・」 マヤは少し上を見上げ、数秒間止まった。 「どうした?」 「いや、何でもないです」 大室には先ほどのマヤの顔は、珍しく嫌がっているように見えた。 数週間後、ドラマの収録が始まった。 いつものようにマヤは順調に役をこなし、泥の中に顔をつける場面も嫌がることなくやっていった。 「すごいですね、あの子」 ふとそんな声が聞こえたので横を向くと、今回のドラマでマヤの役の唯一の友達の役をやっている人物がそこにいた。 この子も大室の事務所のタレントである。 名は水島里香。 「お前が友達役か。弟は生きてるか?」 「だいぶ前に退院しましたよ。お見舞いに来てくれたじゃないですか」 「そうだったっけか」 ふと、大室は昔は思い出す。 そうか、あれからもう4年になるのか。 「それにしても、お前も落ちてきたよな。ついこないだなら主役があたりまえだったのに、まあ、俺のせいでもあるが」 「私なんかまだマシですよ。まだ主役の友達レベルに居座れるんですから」 「そうだな」 「それに、あの時はそっくりな双子の姉弟ということで売り出せましたけど、今じゃあ似なくなってきましたからね」 「だな」 大室と里香はもう一度、マヤの演技を見ていた。 どうやら、違う角度からとりたいとの監督の希望によりもう一度同じ場面をやりなおさなければいけないらしい。 「それにしても上手いですね。どこで育てたんですか?」 「俺は何にもしちゃいねえ。さらにいえばあいつは過去のことも教えてくれそうにない」 「謎ですね」 「本当にそうだ」 「私は、助けるほうでよかったです。いじめる役であんな演技されたら罪悪感で胸がつぶれそうですから」 「本当は主犯っていう設定だけどな」 「それをいわないでください」 収録が終わった後、大室はマヤを助手席に乗せ家に帰っていった。 「今日の演技、どうでした?」 「・・・・・・・・・」 大室は、まるで横には誰にも乗ってないような雰囲気を出しながら、運転に集中していた。 「無視しないでくださいよ」 信号は赤になり、車はゆっくり止まった。 「俺は演出家でも評論家でもないんでね」 「そんなに俺のことが嫌いですか」 「・・・お前が初めて俺の家にきたとき、てっきり虐待にでもあって家出してきたのかと思った。それか親子喧嘩かな」 目の前の横断歩道には何人もの人が歩いていた。 「だけど、違うよな? いったいお前は何で俺のもとに来たんだ?」 マヤは軽くため息をつく。 「・・・俺には芸能人の素質があると確信していたからですよ」 「だけどな、俺が始めてお前を見たとき思った。こいつには芸能界は無理だってな」 「そんなの大室さんの予想でしかないですよ。結果は全然違うんですから」 「そういうことじゃない。俺はお前を芸能界デビューさせたくなかった」 「実力がなさそうに見えたんですか?」 「そうじゃない。俺が大嫌いなタイプの人間だって思ったからだよ」 大室はそこで初めてマヤのほうを向き、最後にこう言った。 「お前、今までどこで何をしてきたんだ?」 数秒、そのままの姿勢で二人とも止まっていた。 後ろからクランクションの音が聞こえる。 どうやら、いつのまにか信号が青に変わっていたらしい。 車はゆっくりと発進していった。 「謎が売りなんでしょ。じゃあ謎のままでいいじゃないですか。手品だってタネが分かれば急につまらなくなる」 「質問を変えよう。先日吉川夏樹とバラエティー番組に出た時があったよな?」 「それがどうしたんですか?」 「その後、吉川夏樹と偶然会ったんだが、俺には怯えてるように見えた。何をしたんだ?」 「だから、むこうが役を俺にとられたことに腹をたてていてそういうことは監督に言ってくれって言っただけで」 「降ろすぞ」 「・・・分かりましたよ。本当はむこうから急に首絞めてきたのでその写真を携帯に収めてやり返したんです」 大室は唖然とした。マヤのいうことのすべてが正しいかどうか分からないが、吉川夏樹はそんなことをしてきたのかと。 いや、それよりそこまで怒らせることをマヤが言ったとも考えられなくなかった。 「写真撮ったのか」 「写真はブレてよく分からなくなってましたけどね」 大室のマンションの駐車場まで帰ってきた。 「むこうから一方的にですよ?」 「分かった」 その夜、大室はネットで中学生ぐらいの行方不明情報を調べていた。 もし、マヤの親が警察に通報していたら何かしらの情報が見つかると思ったからである。 しかし、それっぽい記事はあるものの、どれも時期がマヤとはあてはまらなかった。 それにしても・・・と大室は思う。 今回のいじめられっ子役、マヤは嫌がっていると思ったがかなり素晴らしい演技であった。 まあ、あんな役喜んでやるほうもどうかしてるか。顔に泥を塗るようなことをしなければいけないのだから。 だからといって、いじめるほうをやれば人気度が落ち、一番いいのは助ける側なのだが、そもそもそれが主犯なのだから今回のドラマは出演者にとって過酷である。 さらに今回のドラマは主役がヒーロー的存在ではなく、いじめられている子を好きだけど弱虫で助けられないという、どの人物でも嫌な役になってしまうというこんなドラマ今まであっただろうか? という仕上がりになっている。 それから数日して映画の撮影は終了、ドラマのほうも撮影も順調に進んでいて、ようやくマヤにもゆとりというものがもてる時期になった。 手帳を見ても、休みがかなりある。かなりあるといっても、先月と比較してあるというだけで、一般的に考えればまだまだ仕事は多い。 「今度の休みにでも家に帰ったらどうだ?」 大室は、座椅子にもたれながらテレビを見ているマヤにむかってそう言った。 「そうだな・・・」 大室にとっては少し予想外な言葉が返ってきた。 これだけ家に帰ってないんだ。少しぐらいは実家が恋しくなったのかもしれない。 大室はそんなことを思いながら、少し離れたところで一緒にテレビを見ていた。 それにしても、マヤが見るテレビといえばほとんどニュース番組である。 さらに、マヤはたいてい大室よりも早く起きて先に新聞をチェックしている。 そういえば、前に小さく何かの記事を切り取っていることがあったのを大室は思い出した。 もしかしたら、そこにマヤに関する記事が書いてあったのかもしれない。 休みの日。 マヤは本当の姿、つまり男の格好で一人外に出て行った。 念のためたまに後ろを確認する。 大室はついてきていないようである。 しばらく歩いていると、家まであと10分というところまで来た。 マヤは悩んでいた。 帰るべきか帰らないべきか。 一歩、前に進める。 果たして、自分が家に帰って家族はどう思うだろうか。 本当は帰ってきてほしくないのではないのだろうか。 そんな不安がマヤの頭の中をよぎった。 何分たっただろうか。 その場で立ちすくんだまま、マヤは全く動こうとしなかった。 マヤはそんな自分に気づいたとたん、そんな自分にバカらしくなってきた。 今帰って何になる。一歩間違えれば芸能生活ともおさらばだ。 きっと、家に帰れば不自由な生活になるだろうから・・・。 ――俺はもう一人で生きていける・・・。誰にも迷惑をかけずに・・・。 そんなことを考えながら、マヤは体の向きを180度回転させ、大室の家に帰ろうとした。 ――俺がこの家に帰るのは芸能界を引退したときでいい。 そんなことを考えながら、マヤは足を進ませた。