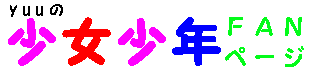第3話~動揺~
「な、なんの、なんのことですか」 飛鳥は眼鏡をとって、眼鏡をいつも使っているメガネ拭きではなく、給食用のナフキンで拭きながら裕司にそう言った。 どう見たって動揺している。 「ごまかすなよ、すっごいキュートだったぜ」 「なななな、何の証拠があってそんなことい、言えるのですか?」 飛鳥自身にも自分自身がどうしようもないぐらい動揺しているということは分かってた。 だが、どうしてもごまかさなければならなかった。 これがバレたら、確実に弱みにつけられる。そう思ったからだ。 「証拠ならあるよ」 裕司はそう言った その一言で、飛鳥は固まった。 もしやあの時、写真でも撮られたのではないかと。可能性がないわけではない。 むしろ、そう遠くない場所でやってたぐらいなのだから誰かが見ていてもおかしくないはずだ。 「証拠は、あんなにかわいい子、飛鳥しか見たことないからさ。俺は飛鳥が好きだから分かる」 「はい?」 その言葉で飛鳥はかなり落ち着きを取り戻した。 どうやら証拠という証拠はないらしい。 「それのどこが証拠というのですか。私は今、勉強中です。邪魔しないでください」 そう言うと飛鳥は眼鏡をつけ、席にしついて社会の問題集を広げた。 その後は、裕司はもう飛鳥に言い寄ってこなかった 放課後、飛鳥はいつもどおり一人で帰っていった。 左手にその日に学校の図書室で借りた小説持っている。信号待ちなどで立ち止まることがあったらすぐに読めるようにしているのだ。 しばらく歩いていると、飛鳥は誰かに肩をトントンと叩かれた。 どうせ裕司であろう。 そう思った飛鳥は「だから、やめてください」と言いながら振り返った。 「悪い悪い」 そこにいたのは、裕司ではなく、大室であった。 「すみません、あなたでしたか。てっきりいつもからかってくる、クラスメートかと思いまして」 「いいよいいよ、それよりこれお礼」 そう言いながら大室は一つの封筒を飛鳥に渡した。 「まあ、少ないけどさ」 「そんな、お礼なんて結構ですよ。まして現金なんて」 飛鳥はその封筒を受け取らないようにした。 「いや、図書券なんだけど。図書券5000円分」 「と、図書券!!」 図書券、それは本と交換することが出来る魔法のような券。 もちろん、参考書だって問題集だって、小説だって・・・。 「まあ、いらないなら別に受け取らなくても」 そう言って、大室はその図書券が入った封筒をカバンにしまおうとした。 「や、や、やっぱ受け取ります。お礼はちゃんと受け取るものだって祖母からも言われてきましたし」 「あっそ、じゃあはい」 そう言って、飛鳥は大室から図書券を受け取った。 「あの、それともう一つ話があるんだ」 「何ですか?」 そう言われ、飛鳥は大室の顔を見ようとした。 その時、大室の後ろにいる裕司の姿が見えた。 「実はね、あのCMをシリーズ化したいらしくて・・・・」 「あの、す、すいません用事思い出したんで、失礼します」 飛鳥は裕司にばれないうちにこの場を去ろうとした。 今、裕司とあったらまずい。飛鳥はそう思って一目散に逃げようとした。ここで、祐司と会いたくない。 だが、その願いは叶わなかった。 「ア・ス・カ、放課後まで飛鳥に会えるなんて俺ついてるかも」 「やめてください、迷惑この上ないです」 裕司はいつもどおり飛鳥にくっついてきた。 それを見ていた大室はこう思う。 「何々? 恋人?」 「違います」 「恋人候補ですけどね」 「ああもう、離れてください」 そんな騒ぎが道の真ん中で行われていた。 そして何秒かたって、裕司は大室の顔をじっと見つめると、 「あれ? もしかしてあなた、芸能プロデューサーの大室哲郎さん?」 そう言った。 その言葉を聞いた飛鳥は、とたんに胸の鼓動が早くなるのを感じた。 裕司が大室が芸能プロデューサーだと知っている。 つまりそれは、今日学校で言ったことを肯定せざるを得ないということになるのではないか。 「そうそう、よく知ってるね~俺も有名になったもんだ」 「あ~やっぱりそうなんだ、やっぱ本物はテレビで見るより」 大室は裕司の言葉の続きを楽しみにしていた。どうせ、かっこいいというだろう。 そういうことは大体予測していたが、 「かっこよくしようとしてるのがバレバレだな~」 大室は少しショックをうけた。 「ちょっと、失礼じゃないですか。もっと言う言葉を考えたらどうですか?」 「だって飛鳥もそう思うだろ」 「そりゃあ、ちょっとは思いますけど、言葉に出していうことではありません」 大室はまたショックを受けた。 「それよりやっぱ飛鳥、今日学校で言ってたことは本当だったんじゃねーか」 「その話はしないでください」 「何の話?」 大室はすこし引きつった顔をしながら二人に聞いた。 「飛鳥が昨日、CMに出てただろって言ったら否定するもんですから」 「あ~やっぱ分かる人には分かるんだね~。さすが恋人候補」 「まあね~アハハハハ」 飛鳥は二人が話している間にこの場から立ち去ろうとした。 だが、いつの間にか裕司の左手が飛鳥のランドセルをつかんでいて逃げることができなかった。 「それより、話があるんだ。実は昨日から放映されたCMのシリーズ化が検討されててさ」 その言葉を聞いて、ものすごい飛鳥は嫌な予感がした。 「正式にうちの事務所でデビューしないかな~? って」 「やりません」 飛鳥はすぐに断わった。 だが、裕司は大室に賛成した。 「やれよ、俺は応援するぜ」 「やりたくないんです」 「そっか~じゃあ、明日、孝一に飛鳥が新しい携帯電話のコマーシャルやってるって教えようかな~?」 「やめてください、それだけはやめてください。そう言うと少しは予想してましたが」 ちなみに、孝一とは裕司の友達の名前である。 「人気が出たらもっと図書券あげるよ」 「変な誘い方しないでください!」 どうやら、大室は飛鳥が図書券好きというのをさっきの行動で推測したらしい。 「正直惜しいんだよな~君がいてくれるとうちの事務所も大いに助かるんだが」 「そうそう、人助けだと思って芸能界デビューしちゃえよ」 飛鳥は大室と裕司二人に責められた。 しかし、ふと飛鳥は大室が自分を女だと思っていることを思い出した。 「すみません大室さん、私が今しょっているランドセルの色を見て何か気づきませんか?」 「色?・・・・・黒だけど」 「そう、黒です。普通、女の子が黒のランドセルを背負うと思いますか?」 大室は少し考えて、「・・・・あまり聞かない」と答えた。 「でしょ、実は私、男なんです」 さすがにこれを言ったら大室も諦めてくれるだろうと飛鳥は考えた。問題は裕司であるが、そちらは後回しだ。 「ああ、男の子なんだ~。まあちょっとそんな感じするな~って思ったけど」 予想外の言葉が返ってきた。 自分のことを女だと思っていたのなら、もうちょっと驚いてもいいと思うのだが。と、飛鳥は思った。 「まあ、いいじゃんいいじゃん男の子でも。よくある話だって~」 飛鳥は唖然とした。 「ですよね~かわいければ男とか女とか関係ないですよね~」 「そうそう、何人かうちの事務所からも男なのに女としてデビューしてる子がいるわけだし、でもこれ秘密だからね」 飛鳥は愕然とした。 自分の身の回りにはこんな人しかいないことに。 「で、今度の土曜日にドラマのオーディションがあるんだけど」 「もちろんやるよな飛鳥」 その二人の言葉には、飛鳥はもう右から左状態であった。 わけもわからず「はい」そう言ってしまっていた。 そして、大室と裕司にとって事は順調に進んでいこうとした